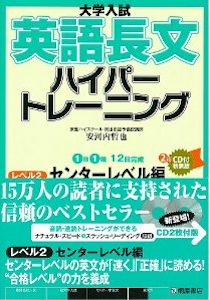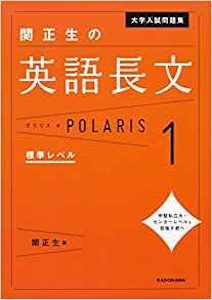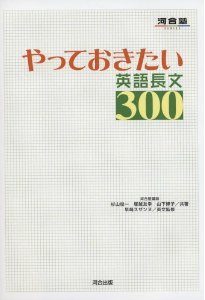今回は日大レベルの英語の長文参考書を紹介していきます。
英語長文の参考書というのもさまざまなシリーズがあり、どれを使えば良いのか、皆さんも悩むのではないでしょうか。
自分にはどのシリーズの参考書が適しているのか、決めかねている方は多いでしょう。
そこで、今回は「このような状況の人にはこの参考書」というように、それぞれのニーズや状況に合わせておすすめの参考書を紹介していきますので、参考にしてみてください。
これから英語長文を学ぶならこの4冊!
の4冊は数ある英語長文の参考書の中でも、特に解説がわかりやすい部類の参考書です。
そのため、参考書MAPでも解説がわかりやすいグループに属しています。
これらの参考書は充実した解説の教材が良いという方におすすめです。
問題の難易度は共通テストレベルのもの、共通テストの基礎となるものになっているので、これから英語長文の勉強を始めようという方はこの4冊で学ぶと良いでしょう。
4つの参考書の共通点
ところで、解説がどれほど詳しいのかという話ですが、これらの参考書にはある共通点があります。
それは、英語の長文全てにSVOCや構文が振ってあることです。
「ここが主語で、ここが動詞。ここからここまでが目的語である」、「この形容詞はこの名詞にかかっている」というように、文章の構造が細かく説明されています。
始めのうちはこの4冊があると非常に勉強しやすくなります。
大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル2
【特徴】
大学入試英語長文ハイパートレーニングレベル2は、共通テストレベルの参考書ではありますが、構文の難易度が少し高くなっています。
そのため、一通り基礎固めが終わった後に共通テストで高得点を狙いたいという方やMARCH・関関同立レベルを目指す受験生におすすめです。
問題と解説が別になっており、収録されている問題数は12題と比較的少なめではありますが、その分解説が詳しくなっているのが特徴です。
また、掲載されている長文が読み上げる音声が収録されたCDが付いているため、CDを聞きながらシャドーイングや速読の練習をすることもできます。
【使用法】
問題を解く際、直接問題集に書き込んでしまうと復習が出来なくなってしまうため、必ずコピーを取ったプリントに書き込んで、答え合わせをするようにしましょう。
また、長文読解問題を演習する際には、ただ問題を解いて満足するのではなく、なぜその答えになるのかという解答の根拠や、考え方のプロセスを意識して使用することがポイントです。
問題の解説を理解し、復習した後は、発音やイントネーション、リズムを暗記するためにCDを聞き、音読していきましょう。
ここでは読むことに夢中にならず、SVOCの構文を意識することが重要です。
大学入試問題集 関正生の英語長文ポラリス1(標準レベル)
【特徴】
関正生の英語長文ポラリス(1 標準レベル)は、日東駒専レベルの中堅私大や共通テストレベルの参考書です。
この参考書の中で取り扱われている長文のテーマは、最近の入試を分析したうえで選出されています。
そのため、最近の傾向に合った英語長文を読む練習をすることができます。
また、ネイティブスピーカーによる英語長文朗読音声のダウンロードをすることができ、シャドーイングやディクテーションをすることが可能です。
【使用法】
まずは問題に挑戦してみましょう。
その途中で分からない単語が出てきたら印を付けておくと後で確認することができて良いです。
また、解き終わったら解説を読み、どうすればその回答に至ることができたかプロセスを考えるようにしましょう。
最後にダウンロード音声を使って音読をすることで、速読の練習をすることができます。
英語長文レベル別問題集4 中級編、英語長文レベル別問題集3 標準篇
【特徴】
英語長文レベル別問題集4 中級編は共通テスト・中堅私大レベル、3の標準篇は共通テスト(基礎)・一般私大レベルとなっています。
この参考書の英文には全ての文にSVOCがふってあるので、「どうしてこの訳になるのか」が徹底的にわかるでしょう。
解説の中には長文に出てくる単語の意味が一覧となっているので、一通りの長文に取り組むことができれば、長文を解くために必要な語彙のレベルが高くなります。
解説がしっかりしている参考書を探している人はこちらがおすすめです。
【使用法】
後で確認することができるように、分からない単語や熟語に印をつけながら問題を解いていきましょう。
解き終わったら、どうすれば正解することができたのかを考えながら丁寧な解説を隅々まで読むと良いです。
その時、問題を解いている間に印を付けた単語や熟語の意味を確認することも忘れないようにしましょう。
そして分からなかった単語や熟語を一つにまとめておくと、自分だけの単語帳を作ることができるのでおすすめです。
英語長文に慣れるにはこの2冊!
の2冊は先ほど紹介した4冊と比べると、全体では解説の面がやや劣ります。
どのように劣るかというと、文章全てにSVOCが振られているわけではありません。
しかし、設問1つ1つに対する解説に関して言えば、かなり充実しています。
例えば、「この問題の答えは~です。なぜなら~だからです。」、「この問題はこのように考えると答えが~になります。」というように、問題に対する解説はとても充実しています。
この2冊は問題数が多い!
この2冊は問題数も多いので、英語の長文をたくさん読んで、演習を重ねていきたいという方におすすめです。
この2冊の参考書の場合、共通テストレベルの単語知識が無いと、解けない問題も出てきます。
解けない問題があるということは、知識が足りていないことを意味しているので、前の参考書に戻って知識をつけましょう。
イチから鍛える英語長文300
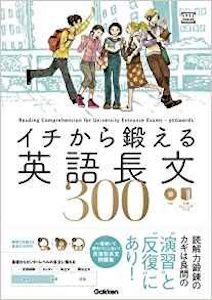
【特徴】
イチから鍛える英語長文300は、長文を一度解いただけで終わらせず、同じ長文を繰り返し読むことで読解力を身につけることができる参考書です。
読解力が身につくように解説が丁寧になされているので、一つ一つじっくり読んで復習しましょう。
また、音読しやすいようにCDが付いているので、文章を何度も音読教材として使うことができます。
音読やシャドーイングを通して、英語長文を素早く読むことができる力を付けることができるでしょう。
【使用法】
まずは問題を解いてみて、どれだけ自分がその文章を読むことができるか確認してみましょう。
要約問題や文脈把握問題が全長文で取り扱われているのでパラグラフごとに簡単な見出しを付けながら読むと時間短縮になります。
そして、解説には構文開設や読み下し訳がついているので、隅々まで解説を読み、自分の読んでいた文と合っていたかどうか確認してください。
音読用のCDが付いているので、何度も繰返し音読して、英語を英語のまま理解する練習をしていきましょう。
やっておきたい英語長文300
【特徴】
やっておきたい英語長文300は、日大レベル・共通テストレベルの実力を付けることができる参考書です。
書名の通り、1題における語数は300語程度なので、「長い長文が苦手」という方でも負担なく読むことができます。
解説の中には入試で出やすいポイントなども解説されているので一つ一つ頭に入れながら勉強を進めましょう。
全部で30題の長文が収録されているので着実に実力を付けたい人におすすめな参考書です。
【使用法】
30題の文章が入っているので、前からどんどん読んで解いていきましょう。
全て解ききると共通テストレベルの長文を難なく読める力が身につきます。
丸付けをした後は解説を読み、どうすれば正解できたかについて解答プロセスを確認する時間を作ると良いです。
解説の中には入試で狙われやすいポイントを解説している部分もあるので、そこで新たに知ったことは書き留めておくと頭に残りやすくなります。
基礎基本から学びたい方はこの1冊!
【特徴】
「入門英語長文問題精講」です。
この参考書はまず、文章レベルがとても易しくなっています。
そのため、出来るだけ易しいレベルから勉強を始めたいという方におすすめです。
解説には前文にSVOC分析が載っており、文構造を一目で確認することができるようになっています。
簡単な問題から解きたいという方はこの参考書を活用してみてください。
【使用法】
この参考書では文法、語彙問題、内容理解問題、要約問題など入試で頻出の様々な問題形式を取り扱っているので、一通り解いてみることで様々な問題形式に慣れることができます。
解説には前文にSVOC分析が載っているので、和訳問題などについては自分の思っていた文構造と同じだったかどうか確認してみましょう。
また、長文の中に出てくる重要語句の意味も解答・解説の中で抑えることができるので、分からなかったものはしっかりと書き留めておくと良いです。
英文読解に関する映像授業がついているので、分からない部分がある人はそれを視聴して分からなかった部分を潰していきましょう。
まとめ
今回は日大レベルの英語長文の参考書をそれぞれ紹介してきました。
状況別に大きく3段階に分けて紹介しましたので、これらの中から自分に適した参考書というのを見つけてほしいと思います。
それぞれの参考書について詳しく紹介している記事もありますので、ぜひご覧ください。