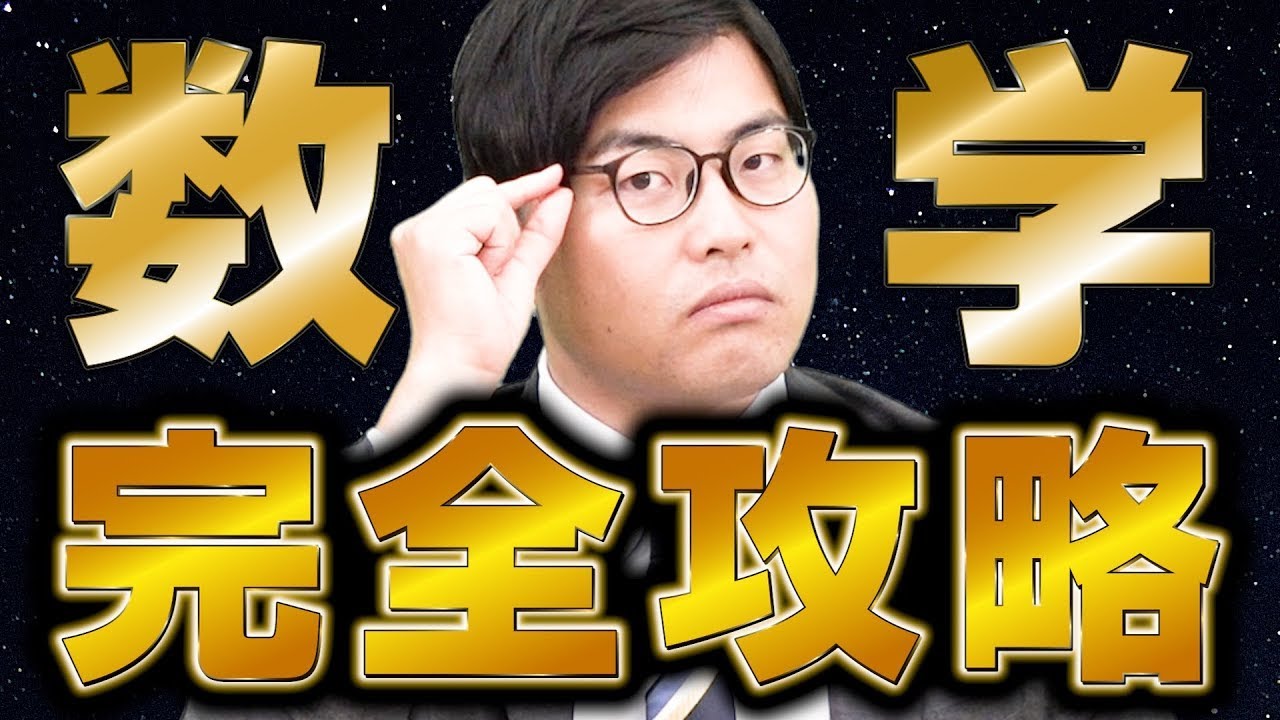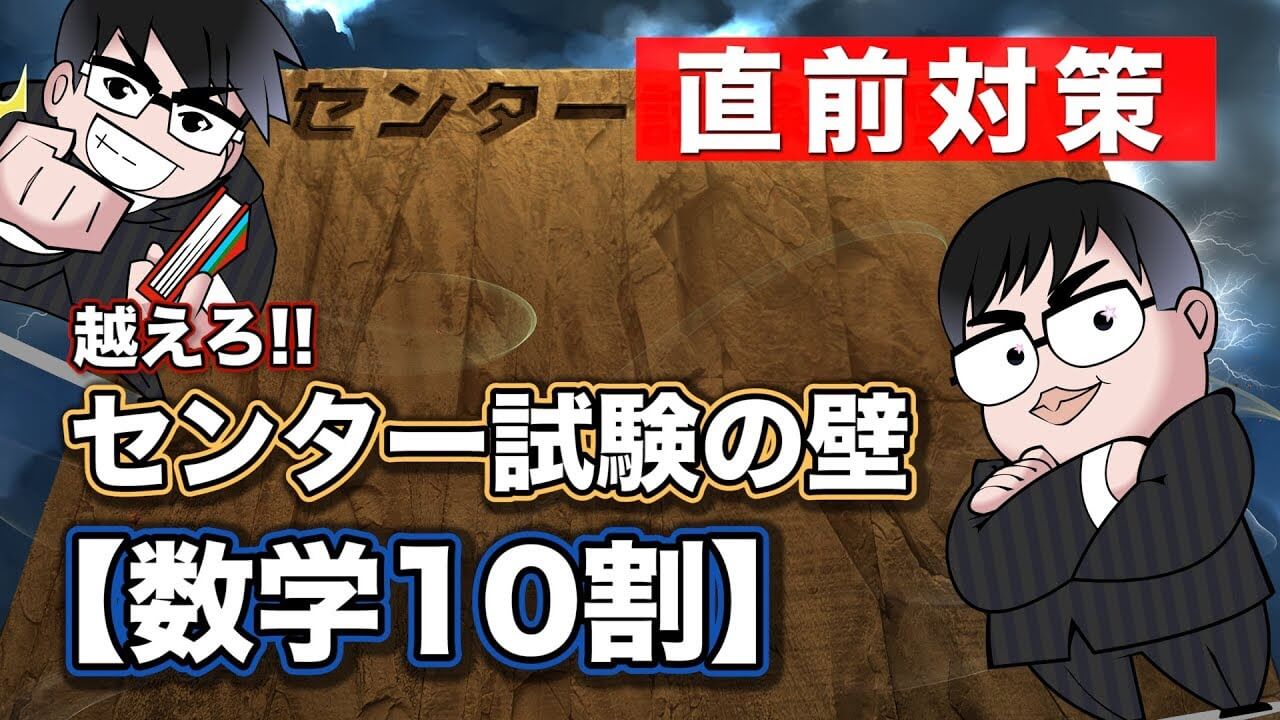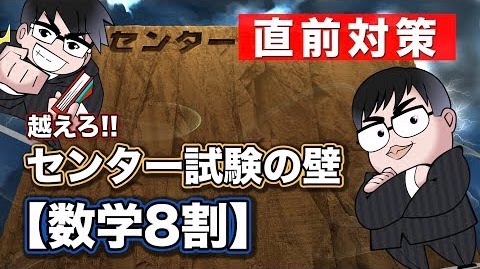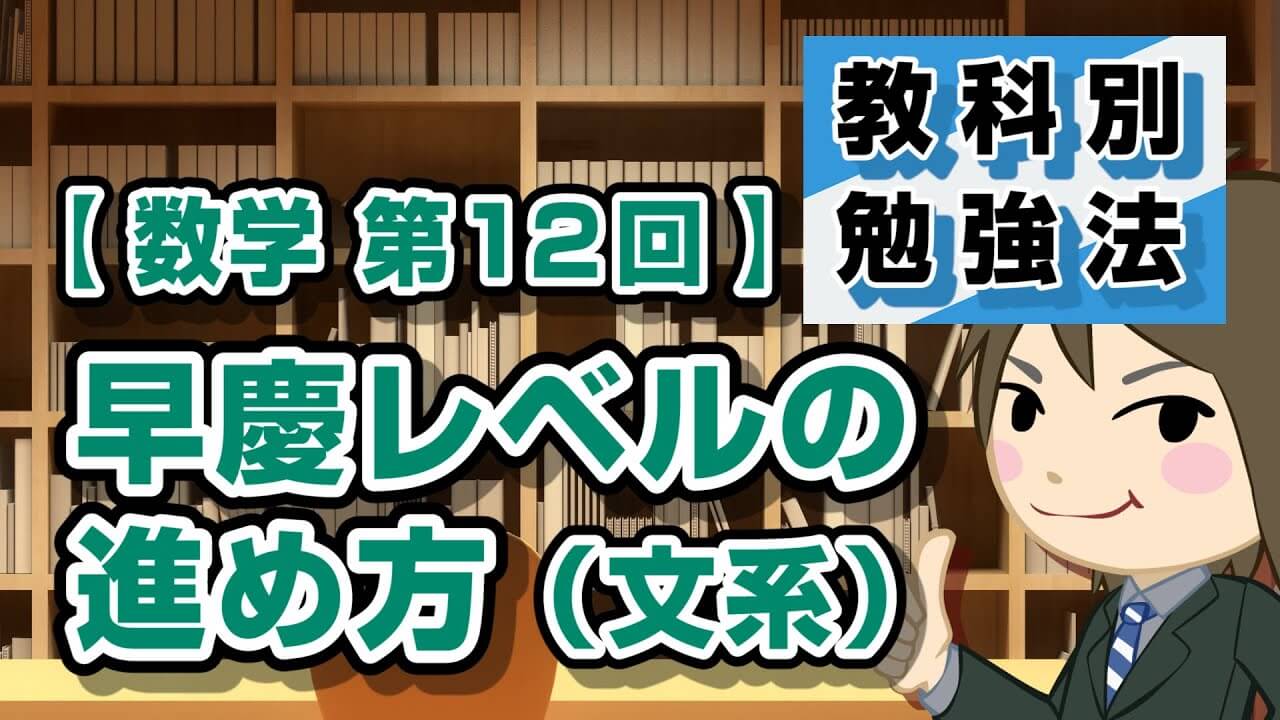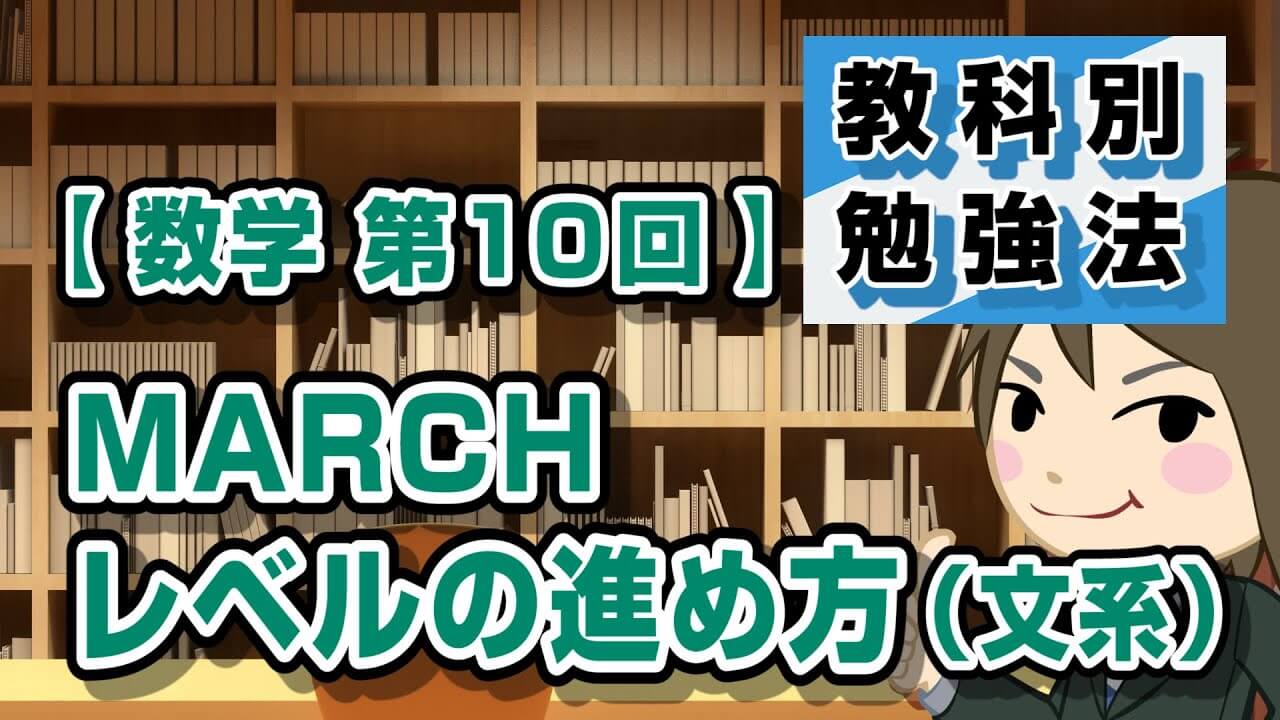「数学の受験勉強を始めたいけど、共通テストと一般入試の違いがよくわからない」
「国公立と私立の違いと、どっちが難しいのかがわからない」
大学受験を考える高校生の中には、このように悩む人は少なくありません。
この記事では、共通テストと一般入試のどっちが難しいかと各試験の違い、問題傾向を整理しつつ、私立大学や国公立大学の受験対策も紹介します。
共通テスト数学の対策で優先すべき単元4つとその勉強法も解説するので、各受験の特徴を踏まえて進路実現を目指しましょう!
共通テストと一般入試の数学はどっちが難しい?違いを解説
共通テストと一般入試の数学は、出題形式も内容も大きく異なります。
まずは両者の違いをしっかり理解しておくことが、正しい勉強法を見つけるには欠かせません。
ここでは、出題形式と問われる力、どっちが難しいか、という3つの観点から、共通テストと一般入試の数学の違いを整理します。
各入試の違いと特徴を知って、受験勉強の第一歩を踏み出しましょう。
出題形式の違い:マーク式と記述式
共通テストと一般入試の主な違いは、出題形式と問題数、試験時間です。
これらの違いは次の表の通りです。
| 共通テスト | 一般入試 | |
|---|---|---|
| 出題形式 | 全問マーク式 | 記述式が中心だが、解答だけでよい問題もある |
| 解答方法 | 選択肢を選ぶか、穴埋めの形で解答 | 式や言葉を使って答案を作成する |
| 特徴 | ・感覚で解ける問題もある ・間違いでも空欄を埋められる設問がある ・問題数が多く、試験時間は70分と短め ・部分点が無い |
・解答の根拠や途中式を書く必要がある ・大問数は少なめで、試験時間は120分程度と長い ・正解でなくとも方針が伝われば部分点がもらえる |
共通テストでは、答えが全然違うのに解答欄に当てはまったり、分数の解答位置を間違えたりと、マーク形式ならではのミスに注意が必要です。
また、問題の文量がかなり多い一方で試験時間は少なめです。素早く情報を処理して解き進めましょう。
一方で一般入試は問題数が少なく、じっくり考えて問題に取り組むことができます。
各大問ごとの前半の小問は、後半の小問を解くヒントにあたります。
計算を進めるための誘導にうまく乗り、自身の考えをその場でまとめる対応力が必要です。
問われる力の違い:読解力&処理力と論理力&記述力
共通テストでは、問題文やグラフ等を読み取る読解力と、たくさんの情報を素早く処理する力が問われます。
限られた時間内で問題の文脈理解と素早く正確な計算を、行う練習が必要です。
対して一般入試では、解答の構成を論理的にまとめる力や、途中式を使って答案を書き上げる記述力が重視されます。
根拠と論理を組み合わせて、自分の考えを説明する訓練を積んでいきましょう。
難易度の違い:どっちが難しいかは個々の状況次第
共通テストと一般入試のどっちが難しいかを断言することはできません。
共通テストは情報処理力と時間管理に不安があるなら難しいと感じるでしょうし、一般入試は応用力と記述力に課題があるなら壁になります。
共通テストはスピード勝負であり、焦りから生まれるミスが命取りになりやすいため、急ぎながらも計算を正確に進める冷静さが必要です。
国公立などの一般入試はそれぞれの問題が重く、記述の完成度で差がつくため、問題ごとに解答の方針を考える思考力が求められます。
自分には共通テストと一般入試試験どちらの方が課題が大きいかなどで判断するなど、出題傾向を分析しながら対策を立てることも大切です。
共通テスト数学の特徴と対策のコツ
共通テストの数学は、全問マーク形式で問題数が多いことが特徴です。
文章量が多いうえに、図表や会話文から素早く意味をつかまないといけない問題も多いため、読み解く力や情報処理能力が問われます。
ここでは、共通テスト数学の問題傾向と必要な力、効果的な勉強法の3つを解説します。
マーク式解答で初見の知識を使う問題がある
共通テスト数学はマーク式解答であり、出題される問題は基礎的な計算と会話文や図表の読み取り、データの分析などです。
計算に使う初見の知識が問題文に書かれている場合もあり、覚えている公式と上手く組み合わせて解き進める力が求められます。
試験時間に対して問題量がかなり多いため、次々と問題を読んで処理する訓練を積んで対策しましょう。
問題の分量・出題数が多い
70分の試験時間に対して問題の文量と出題数が多いため、素早く文章を読んで情報を整理する情報処理力が必要です。
マークシートに解答を記入する時間を考えると、実際に問題に取り組める時間は60分程度と考えてよいでしょう。
一方で、スピードだけを意識すると計算ミスが増えてしまうため、正確な計算を進める意識も重要になります。
情報処理力と正確な計算力はすぐには身につかないので、過去問や対策問題集などを活用し、十分に練習を積んで問題の形式に慣れておくことが大切です。
教科書レベルの基礎力を固めるために効果的な勉強法
効果的な勉強法として、教科書レベルの基礎力を確実に固めることが挙げられます。
その上で、過去問や共通テスト形式の予想問題を活用することも大切です。
問題の形式に慣れるためにじっくり解いたり、素早さを意識して時間を計って取り組んだりと、幅広い活用法があります。
練習を通して自分の得意分野や間違い方の傾向を見つけることで、より効率よく対策を進めることが可能です。
私立大学の数学の特徴と対策のコツ
私立大学の数学は記述解答が少なく、空所補充式や選択式の問題が多い傾向にあります。
さらに大学ごとの個性が強く、出題形式や頻出単元が大きく異なる点も大きな特徴です。
ここでは、私立大学入試の問題傾向と特徴、大学ごとの違いと効率的な勉強法について解説します。
空所補充式や選択式が中心でやや応用的な内容も含まれる
私立大学の数学は、空所補充式や選択式が中心で、途中式の記述を求めない形式が多く見られます。
出題レベルは教科書の標準問題程度ですが、難関私立大学ではやや応用的な内容が含まれることもあります。
記述式の入試に比べると取り組みやすい一方で計算量や設問数が多いため、ある程度正確な処理力とスピードが必要です。
大学ごとに個性が異なる
私立大学は、大学ごとに出題傾向や頻出の分野が異なるといった個性があります。
さらに、同じ大学の同じ学部学科でも、入試の出願方式によって問題の難易度が変わります。
対策として、幅広い分野の勉強を進めると同時に、志望大学の赤本に取り組んで問題傾向をつかむことが必要です。
傾向をつかむことで一定の単元に特化した演習ができるため、効率よく対策が進められます。
各大学の演習をするための効率的な勉強法
効率的に勉強を進めるためには、各大学の赤本と頻出単元の演習ができる参考書がおすすめです。
まずは赤本で大学ごとの問題傾向や難易度、頻出分野を把握しましょう。
続いて演習用の参考書を使って、各分野でのパターン問題の解法を習得することが大切です。
特に数列、確率、ベクトル、微積分などの分野は重点的な対策が求められます。
初見問題に強くなるよりも、頻出のパターンに慣れ、問題を見た瞬間に解法が浮かぶ状態を目指すことが合格への近道です。
国公立大学の数学の特徴と対策のコツ
国公立大学の数学は、記述式解答の問題が中心です。
途中式や適切な言葉を補いながら答案を作成するため、正確な計算力はもちろん、自身の考えをまとめ上げる総合力が求められます。
ここでは、国公立大数学の特徴や差が付くポイント、頻出テーマや効果的な勉強法について解説します。
記述式中心で解答までの過程も評価対象になる
記述式解答の問題では、最終的な答えに加えて、解答に至るまでの過程や考えも評価の対象です。
計算問題か証明問題かを問わず、どのような方針で解き進めていくか、問題文のどの情報を使い計算するかを、数式と言葉でまとめる必要があります。
試験本番で確実に得点するために、正確な計算力の向上に加えて、考えをまとめて説明することを意識して演習に取り組みましょう。
幅広い分野での難問がそろっている
微分積分や方程式、確率や整数問題に数列、ベクトルに複素数平面など、幅広い分野での難問がそろっており、まさに数学の総合力が問われます。
全体的に少なめの大問と複数の小問で構成されていて、小問の誘導に乗りつつ部分点を積み上げることが基本戦略です。
旧帝大レベルではかなり高度な発想を要求されるため、十分な演習を重ねましょう。
遺産力と記述力を高めるための効果的な勉強法
計算力と記述力を高めるために、まずは教科書レベルの基礎から確実に理解を深めましょう。
その後受験対策用の問題集で演習を重ね実力を伸ばし、各大学の赤本に取り組みます。
赤本で問題傾向をつかんだ後はまた演習に戻り、実践を意識しながら答案作成の練習を繰り返し重ねましょう。
答案作成に関わる力は一朝一夕で身につかないので、早めにかつ計画的に取り組むことが重要です。
共通テスト対策でまず取り組みたい単元と勉強法
一般入試は大学や学部ごとに内容が異なりますが、共通テストは志望大学に関わらず試験内容や出題傾向が同じです。
共通テストは2025年度から新課程に合わせて出題範囲や傾向が変わりましたが、以前の問題と比べてどっちが難しいか断言はできません。
マーク式解答はそのままに、問題の文量や計算量が増加したため、事前の演習がより重要になりました。
ここでは、共通テスト対策でまず取り組んでおきたい4つの単元として、2次関数と場合の数、指数関数・対数関数と数列をピックアップしました。
それぞれの学習ポイントと勉強法を確認しましょう。
数学ⅠA①:2次関数
文字を含む2次関数の最大値と最小値、軸との共有点などを問う基本問題に加え、数式ソフトを利用したグラフの形状変化を問う応用問題など、内容は多岐にわたります。
2次方程式やその解とも密接な関係があるため、平方完成やグラフの性質といった基礎を確実に身につけ、2次関数を道具として利用できるほどの実力をつけましょう。
数学ⅠA②:場合の数と確率
この単元は毎年のように出題され、条件整理や情報処理の力が問われます。
自然数nを用いて一般化された確率を求める問題がほとんどですが、まずは具体的な数で計算をして、問題で問われている内容のイメージをつかむことが大切です。
マーク形式では、答えが間違っていても解答欄にあてはまってしまうことが多々あるため、その点も注意が必要です。
数学ⅡBC①:指数関数・対数関数
指数関数と対数関数はセットで扱われることが多く、グラフの形や性質も対になっています。
これらの関数を含む2次関数の問題も出題されており、他の単元へ組み込んだ問題が作られやすいことも大きな特徴です。
指数計算や対数の定義など、基礎の内容を確実に押さえておくことで、別の分野と混ぜた応用問題にも対応できるようになります。
数学ⅡBC②:数列
3問ある選択問題の1つで、比較的選ばれやすい単元のため、十分な対策が必要です。
実生活の出来事を数列で分析する問題が出題されており、中には複雑な漸化式が登場することもあります。
漸化式の変形にあたって誘導がつけられていることがあるため、問題の計算方針に従いながら、少しずつ確実に解き進めましょう。
漸化式の問題はパターンが非常に多くありますが、試験までに参考書で十分な演習を重ねることで、得点源として期待できる単元です。
共通テストと一般入試の数学の違いとは?まとめ
私立の共通テストと国公立の一般入試では、求められる力や対策方法、問題の傾向が大きく異なります。
そのため、どっちが難しいかは受験生によって異なり、断言することはできません。
私立の共通テストではマーク形式の問題で、素早く正確に情報を処理する力が必要です。
私立大学では学校ごとの個性を知り、それにあった演習を重ねるなどの対策が効果的です。
国公立大学では、記述力をはじめとした数学の総合力が問われます。
どの形式の試験でも、各入試で求められる数学の力を知り、それに合った勉強法で演習を積み重ねて力を伸ばすことが大切です。
>綿密な準備と対策を通して、受験の合格を勝ち取りましょう!