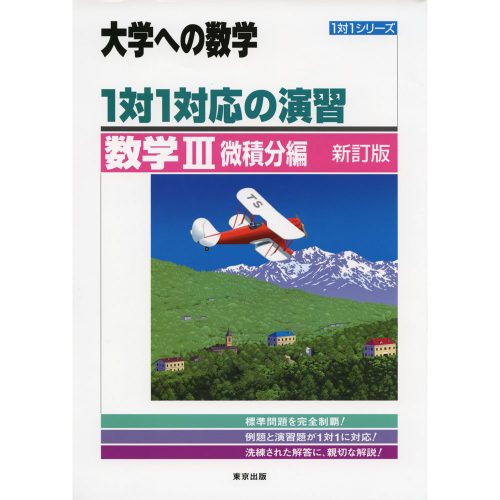「数学の公式がなかなか覚えられない」
「大学受験に向けて、数学の勉強は何から始めればいいか分からない」
大学受験に向けた対策を始める高校生には、このような悩みをもつ人も少なくありません。
公式を効率的に身につけて大学受験に向けた対策をしっかり進めるためにも、正しい数学のインプット法・勉強法を知ることが大切です。
この記事では、数学のインプットがうまくいかない理由を整理し、効率的な勉強法とインプットにおすすめの参考書を3冊紹介します。
大学群ごとに求められる学力レベルも紹介するので、自分の志望する大学と比較して参考にしてください。
正しいインプットのやり方と勉強法を知って、大学受験に向けたよいスタートを切りましょう!
数学のインプットがうまくいかない原因3選
頑張って覚えているのに数学の公式が頭に残らないと悩む人には、いくつかの共通した原因があります。
ここでは、インプットがうまくいかないやり方と、その背景にある思考のくせを解説します。
効率的に勉強を進めるために、当てはまっているものがないか確認してみましょう。
感覚や雰囲気で公式を暗記したつもりでいる
頑張って覚えているつもりなのに、実際はなんとなくでしか覚えられていないという事がよくあります。
例えば2乗があるかどうか、符号はなにで係数はいくつか、などの細かくて大切なポイントを押さえず、公式を見た目で大まかに覚えるようなやり方では「インプットができた」とは言えません。
数学には直感を働かせると有利になる場面もありますが、暗記の場合は話が別です。
感覚や雰囲気ではなく、文字や図の意味を理解しつつ、細かいところも意識して覚える勉強法に切り替えましょう。
公式を丸暗記しようとしている
教科書通りに書いてあるものを丸暗記するやり方は、質の良いインプットとはいえず、覚えたつもりになってもすぐに抜け落ちてしまいます。
2次関数の平方完成を例に挙げると、なぜその変形をするのか、変形の途中でどんな計算が行われているのかなどを考えることで、深い理解と確実な定着につながります。
公式の背景や導出の流れを一度でも納得できれば、忘れにくくなるうえに他の問題で応用がしやすくなるでしょう。
表面的な暗記というやり方ではなく、しっかり考えを深めることが大切です。
一度暗記しただけで満足している
一度きりで暗記したつもりになって勉強を終えてしまうことも、インプットのやり方としては誤りです。
一度覚えた公式でも、時間が経てば思ったよりも忘れてしまいます。
人の脳は繰り返し入ってくる情報を大事なものと認識するため、反復によってより記憶に定着します。
定期的に参考書で公式を見返すなど、インプットしたい情報に触れる機会を意識して作るやり方が有効です。
数学の公式を覚えるための効果的な3つのインプット法
公式はただ見るだけではなく、導出方法や公式の使い方もセットで覚えることで、効率的にインプットすることができます。
ここでは、数学の公式を確実に身につけるためのおすすめのインプット法・勉強法を3つ紹介します。
どれも簡単なテクニックなので、ぜひ日々の勉強に取り入れてみてくださいね。
公式を導出する流れを理解する
公式は形だけ覚えるのではなく、その形になるまでの流れを理解することが、より記憶に残り確実な定着につながるやり方です。
教科書や参考書には、公式の紹介と同時に導出や証明も書かれています。
式変形の流れを意識しながら書き写すことで、公式のインプットはもちろん、計算力も向上できるでしょう。
知識の土台をしっかり固めることで応用問題にも対応しやすくなり、効率的に受験勉強を進められるようになります。
問題演習と組み合わせて暗記する
インプットを効率的に進めるために、アウトプットに取り組むことも有効なやり方です。
人は思い出すことで記憶が強化されるので、覚えた公式を問題演習で繰り返し使いましょう。
最初は参考書などで確認しながら、多くの問題に取り組んで公式を使う機会をたくさん作る勉強法がおすすめです。
「公式を証明しなさい」という問題では、解きながら公式の意味を理解し、自分の中にしっかり落とし込みましょう。
適切な参考書を使う
効率よく公式を覚えるには、暗記に適した構成の参考書を選ぶことも重要です。
使い方や例題がセットになった参考書を使えば、理解と暗記を同時に進められます。
特に重要な公式を厳選して内容が整理されているものは、反復学習にも適しており、長く勉強を継続するのに最適です。
効率的にインプットを進めて実践力を伸ばすためには、適切な参考書選びも重要なポイントです。
インプットにおすすめの参考書3選を紹介
高校2年生から本格的に大学受験の数学対策を始めるなら、参考書選びとそのやり方が重要です。
今の自分のレベルに合った参考書を選び、正しい順序とやり方で進めることで、効率的なインプットが可能です。
ここでは、数学のインプットにおすすめの参考書を3冊紹介します。
ぜひ手に取って、大学受験に向けた数学の勉強をスタートさせましょう。
『青チャート』:教科書の理解を深める基本書

基礎から難関大レベルまで網羅した定番の数学参考書です。
| レベル | 教科書基礎~共通テスト~難関大の標準レベルまで対応 |
| 特徴 | 網羅性が高く、例題・練習問題が豊富。公式の使い方を丁寧に解説 |
| おすすめの人 | 基礎をおさえた後に標準~応用レベルまで広げたい人 体系的に数学を整理したい人 |
| やり方のコツ | ① 例題を1つずつ丁寧に解く ② 解けなかった問題はチェックをつけて繰り返す ③ 問題の型を覚えて応用に活かす |
| 価格 | 税込み 1,375~2,541 円 ※数学Ⅰ、数学A、数学Ⅰ+ Aなど、種類によって値段が異なる |
| ページ数 | 本冊:208~824ページ、解答:128~632ページ |
例題を中心に丁寧な解説がついており、段階的に理解を深められます。
問題数がかなり多いため、全て解くのではなく、まずは例題を解いて公式の使い方や解法の流れや考え方を理解する勉強法がおすすめです。
間違えた問題の解き直しや、辞書のように重要事項を確認することにも使えるので、目的に合わせて取り組み方を工夫してください。
『1対1対応の演習』:公式を使いこなす力を養う
青チャートなどで基礎を固めた後に取り組む発展的な問題集です。
| レベル | 教科書基礎~難関大学レベルまで段階的に対応 |
| 特徴 | 例題と演習題が1対1で対応している。解法の流れが丁寧で、応用力も育つ |
| おすすめの人 | 基礎から応用までを1冊でつなげたい人 自分の手でしっかりと問題を解きたい人 |
| やり方のコツ | ① まず例題をノートに解き写して丁寧に理解する ② 自力で演習問題を解く ③ 間違えたら例題に戻って復習 |
| 価格 | 税込み 1,210~1,760 円 ※科目によって値段が異なる |
| ページ数 | 109~163ページ |
例題と演習題で構成されており、旧帝大や早慶などの難関大対策に最適です。
まずは例題にしっかり取り組み、解法を確実に理解して定着させることがおすすめの勉強法です。
演習題は実戦力を養う難問ばかりなので、基礎力を固めた状態で取り組んでください。
より高いレベルのインプットを目的にしている参考書のため、難しいと感じたら教科書や別の参考書で基礎を見直す必要があります。
『ミニマム数学公式集80』:暗記量を減らして必要最低限を押さえる

数学で頻出度と汎用性の高い公式だけを厳選し、暗記量を最小限に抑えた効率重視の公式集です。
| レベル | 数学ⅠAⅡBを中心とした大学受験基礎レベルの公式に対応 |
| 特徴 | 重要な公式だけを80個厳選した無駄のない構成 |
| おすすめの人 | 公式の暗記が苦手な人 どの公式を覚えるべきか分からない人 スキマ時間で勉強したい人 |
| やり方のコツ | ① 1日数個ずつ覚えていく ② 覚えた公式は実際の問題で使ってみる ③ 穴埋めや書き出しでアウトプット学習を取り入れる |
| 価格 | 税込み 1,078 円 |
| ページ数 | 160ページ |
特に重要な公式を「ミニマム公式80」として厳選しており、例題で使い方を学ぶ勉強法がおすすめです。
参考書全体で200個以上の公式が紹介されているので、苦手な分野や応用力を高めたい分野への対策にも最適です。
別の参考書で問題演習をするときに、辞書のように使うことで、より確実に公式を定着させましょう。
数学インプットのレベルと勉強法を大学群ごとに紹介
ひとことに受験対策といっても、やみくもに進めていては効率的なインプットはできません。
なんとなくでも目標とする大学を決め、実際の大学入試で求められるレベルを知ることで、より力を伸ばせる勉強法が確立できます。
ここでは、有名私立大学や国公立大学入試の出題傾向を紹介し、最低限取り組みたいインプットのレベルを、紹介した参考書の基準で大学群ごとに解説します。
志望校の決定や勉強計画の組み立ての参考にしてください。
日東駒専・産近甲龍レベル
このレベルの大学では、標準的な教科書レベルから基礎問題の応用程度までが中心に出題されます。
典型問題が多く、出題パターンを把握していれば得点しやすい傾向があります。
インプットの目標は、教科書の公式と青チャートの基本例題レベルを確実に理解している状態です。
網羅系参考書は例題中心に取り組み、頻出公式を使いこなせるようにしましょう。
MARCH・関関同立レベル
出題のバリエーションが豊富で、標準問題に加えてやや複雑な誘導や文章題も見られます。
基礎的な知識や計算力だけでなく、応用力や考察力も求められるのが特徴です。
インプットでは、青チャートの重要例題から演習例題レベルが必要です。
典型問題を確実に解ききるために、例題の解法パターンを意識して繰り返し演習しましょう。
旧帝大・東大京大レベル
出題内容は教科書の範囲内に収まるものの、論理力や構成力が問われる記述式の難問が中心です。
複数の分野が融合した問題も多く、各単元への深い理解と柔軟な応用力が求められます。
インプットのレベルは、青チャートから1対1対応の演習まで徹底的にやり込むことが前提になります。
公式を丸暗記するのではなく、導出の流れや意味も理解することで、高い実践力を手に入れましょう。
まとめ
数学のインプットがうまくできないと悩む人でも、目標とする大学のレベルに合わせて、自分に合った正しいやり方・勉強法と参考書を選べば、効率的に実力を伸ばせます。
やみくもに公式を暗記するだけではなく、公式の意味や導出過程を理解することが応用力を磨くうえでも重要です。
今回紹介した参考書を活用して、自分の理解を丁寧に積み上げていけば、大学受験でも通用する力が育っていきます。
まずは志望大学の出題傾向を把握し、自分に足りない力を明確にした上で、効果的なインプット方法の実践が大切です。
正しい勉強法を身につけて、大学受験成功への第一歩を踏み出しましょう!