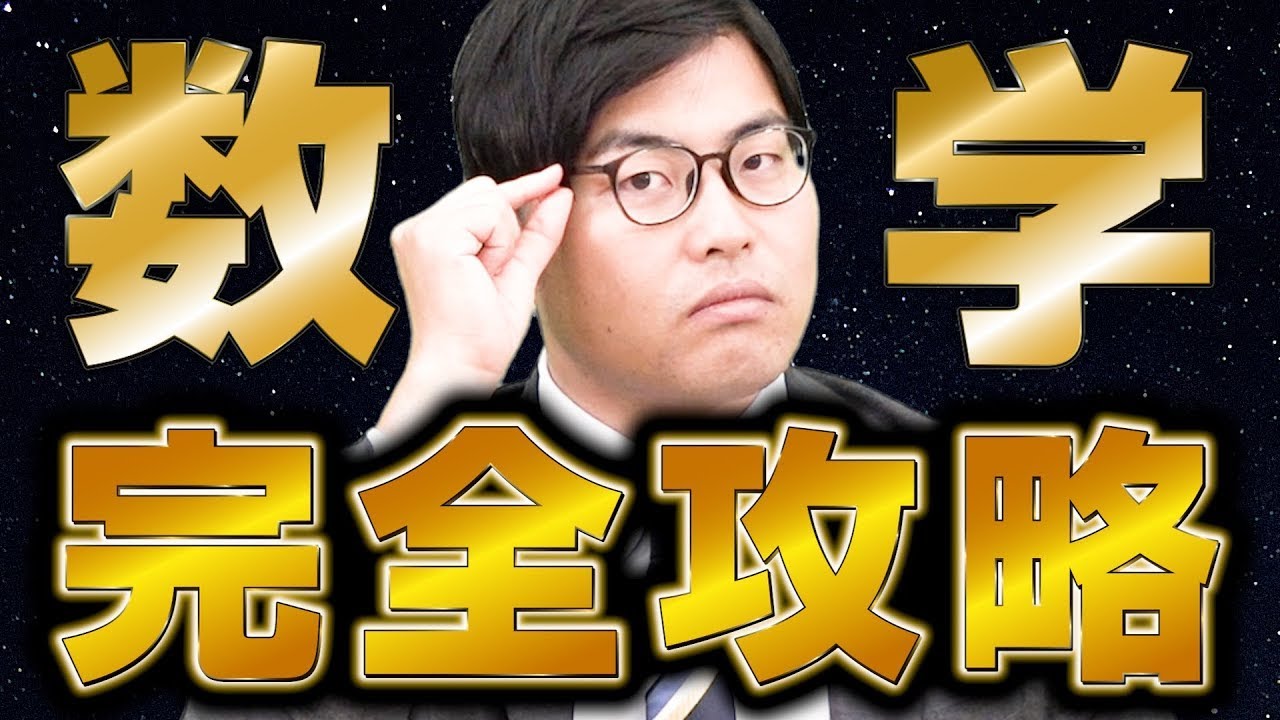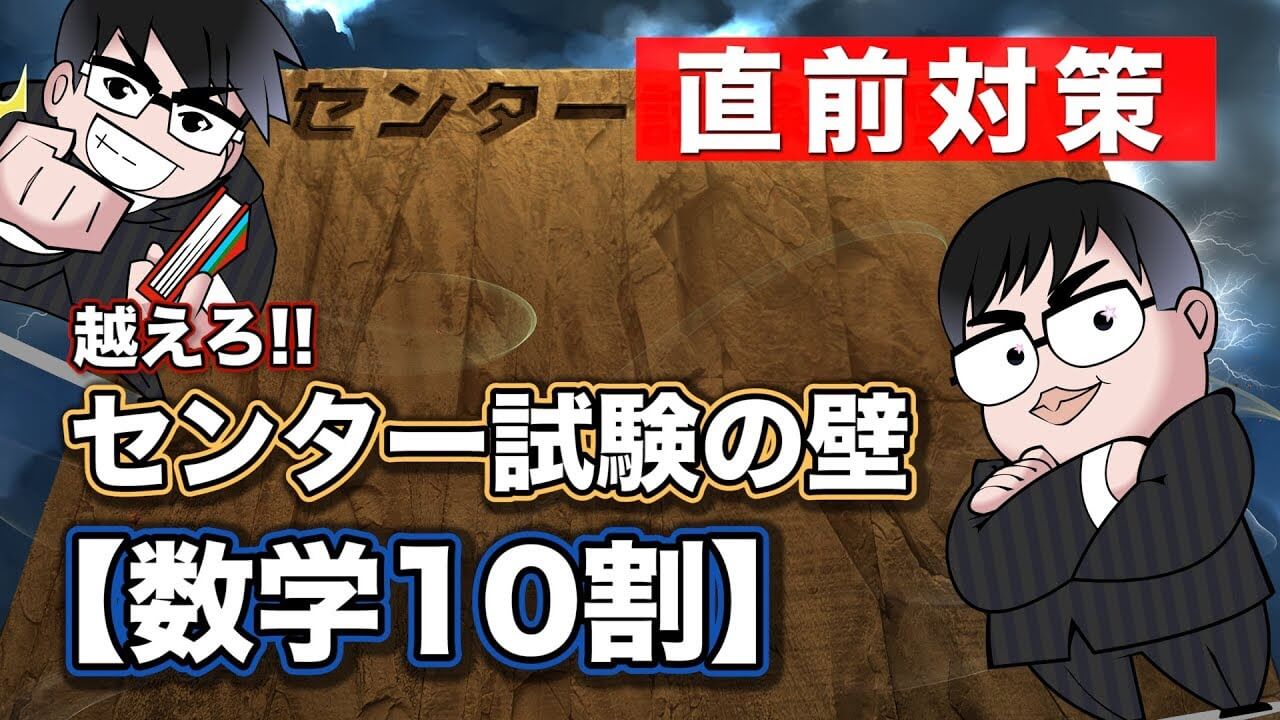共通テスト数学の選択問題について「2025年から何が変わるのか」「なくなる単元はあるのか」と不安を抱く受験生は多いはずです。
結論から言えば、2025年の共通テスト数学の選択問題は新課程に対応することになり、一部の範囲が削除されます。また、制限時間も一部変わるので、出題内容に大きく変更があります。
この記事では、変更の背景・理由・受験生への影響を整理し、具体的な勉強法や対策を提示します。
この記事を読むことで、受験勉強の優先順位をつけやすくなり、無駄な学習を減らしながら得点力を上げる道筋を理解できるでしょう。
2025年の共通テスト数学の選択問題とは?
2025年の共通テスト数学の大きな特徴の一つに「選択問題」があります。
数学ⅠAでは必答問題に加え、複数の分野から選んで解答する形式が導入されています。
これまでの例では、「整数の性質」「図形と計量」「場合の数と確率」などが候補に含まれていました。
数学IIBも同様に「数列」「ベクトル」「統計」などから選択する仕組みがあり、受験生の履修状況や得意不得意に合わせて解答できるよう工夫されています。
この形式があるおかげで、生徒は「履修した範囲に沿って受験できる」という柔軟性を確保できます。
一方で、出題範囲の広さから「どこまで勉強すべきか迷う」という声も少なくありませんでした。
そこで2025年からの新課程導入を機に、出題範囲や選択肢の整理が行われます。
2025年の共通テスト数学の変更点
従来の共通テストと新課程の共通テストを比べて、違いを数ⅠAから順番に確認していきましょう。
数ⅠAの変更点:「整数の性質」の削除
| 【数ⅠA】 | 従来のテスト | 新課程のテスト |
|---|---|---|
| 第1問 | 数と式 図形と計量 |
数と式 図形と計量 |
| 第2問 | 二次関数 データの分析 |
二次関数 データの分析 |
| 第3問 | ★場合の数と確立 | 図形の性質 |
| 第4問 | ★整数の性質 | 場合の数と確立 |
| 第5問 | ★図形の性質 |
※★のうちから2つ選んで回答
もっとも大きな変更は、数学ⅠAにおいて「整数の性質」が削除されることです。
一方で、数Ⅰ分野の出題範囲には変更がありません。
整数問題は面白さがある一方で、特殊な考え方を要するため、苦手とする生徒も多くいました。
入試本番での差がつきやすい反面、「共通テストが本当に測りたい基礎学力」とは少しずれているという指摘もあったのです。
このため、2025年からは整数の性質が出題範囲から外れ、代わりにより多くの受験生が履修する分野に重点が移されます。
数ⅡBの変更点:制限時間の変更と数学Cの登場
数ⅡBは、新課程になるにあたり、数ⅡBCに変更になり、制限時間も60分から70分に変更になり、新たに数学Cの内容のものが出題されるようになりました。
| 【数ⅡB】 | 従来のテスト | 新課程のテスト |
|---|---|---|
| 第1問 | 三角関数/図形と方程式 指数関数・対数関数 |
三角関数 |
| 第2問 | 微分法 積分法 |
指数関数・対数関数 |
| 第3問 | ☆確率分布と統計的な推測 | 微分・積分の考え |
| 第4問 | ☆数列 | ◎数列 |
| 第5問 | ☆ベクトル | ◎統計的な推測 |
| 第6問 | ◎ベクトル | |
| 第7問 | ◎平面上の曲線と複素数平面 |
☆のうちから2つ選んで回答する。
◎のうちから3つ選んで回答する。
また、数学Cが新設され、ベクトルや行列といった分野が整理されます。
これまで数学II・Bに含まれていた内容が移動することで、テストの構成が変わっています。
上記でも新課程の第6問、第7問は数Cの分野になります。
2025年共通テスト数学が変更された背景と理由
2025年から共通テストの数学の範囲や出題内容が変更されたのには3つの理由があると言われています。
第一に、学習指導要領の改訂があります。
2025年入試からは新課程が完全に導入されるため、高校の授業内容に合わせて試験範囲を整理する必要がありました。
第二に、共通テストの理念があります。
共通テストは単なる知識の確認ではなく、身近な状況を題材に数学を使えるかどうかを問う試験です。
そのため、整数の性質のように一部の受験生にしか役立たない内容は重視されにくくなったといえます。
第三に、受験生の負担軽減です。
選択範囲を整理することで、「どの単元をやるべきか迷う」という状況を防ぎ、全員が公平に準備できるように意図されています。
2025年の共通テスト数学の変更による影響
2025年共通テスト「数学」では、出題範囲や内容、制限時間が延長されるなど大幅な変更がありました。
では、これらの変更は受験生にとってどのような影響があるのでしょうか。
勉強時間を効率化!削除範囲で浮いた時間を有効活用
整数の性質がなくなるため、共通テストに限ればその分の勉強は不要になります。
これは勉強時間を効率的に振り分けられるという意味で大きなメリットです。
なくなる分の学習時間を必出分野であり、得点差が出やすい「場合の数と確率」「数列」「ベクトル」に充てることで合否に直結しやすくなります。
このように学習範囲を精査し、より効率的に得点するための勉強スケジュールが組めるようになります。
2025年の共通テスト数学の選択問題の対策と勉強法
ここからは、共通テスト「数学」の変更に伴い、どのように勉強法が変わるのかについて説明をします。
「整数の性質」がなくなる分、どの単元に力を入れるべきなのでしょうか?
1. 出題頻度の高い単元・自分の苦手な単元を優先
「整数の性質」の出題はなくなるため、「確率」や「データの分析」など毎年出題される分野に重点を置きましょう。
特に「確率分布」「期待値」などは典型的な得点源です。
一方で、新しく加わった内容など出題の方向性が決まっていないものもあります。
これらは出題傾向が不明瞭なため、基礎力を養い、安定した得点になるように準備しておきましょう。
自分の苦手な単元を減らすためにも基礎の徹底は重要です。
2. 演習は「図表化」を意識
文章問題や確率問題は、条件を整理して図表にまとめることで理解が深まります。
たとえばサイコロの出る目を樹形図にする、場合分けを表にまとめる、といった工夫をすれば分かりやすくなるでしょう。
共通テストは情報を整理して、解答に導く力が問われています。
自分の考えを図表化する演習をすることで、問題の情報を早く正確に処理できる力がつき、出題形式が変わっても対応することができるようになります。
3. 思考の過程を説明する練習
問題を解くとき、答えだけでなく「どう考えたか」を紙に書き残す練習をすると効果的です。
共通テストは途中経過を重視する傾向があるため、思考を整理する力が高得点に直結します。
復習する際に、自分がどこで間違えたのかが分かり、効率的に対策できるでしょう。
特に新しく出題される範囲の演習に効果的です。
今後やらなくてよい勉強とは?
2025年以降の共通テストにおいては、「整数の性質」を入試レベルで深追いする必要はありません。
もちろん難関大学の二次試験では役立つ場合もありますが、共通テストだけを考えるなら優先度は低いといえます。
その分、「確率」「データ分析」「ベクトル」などの定番分野を徹底する方が得点につながります。
つまり、出題されない範囲を切り捨て、残る範囲を強化する戦略が求められるのです。
2025年の共通テスト「数学」の変更点とは?まとめ
共通テスト 数学 選択問題について、2025年の変更点を背景・理由・影響を含めて解説しました。
「整数の性質」がなくなり、「図形の性質」と「場合の数と確率」に集中することになりました。
また、数ⅡBでは、「数ⅡBC」へ変更され、出題内容や制限時間も大幅に変更されました。
これらの変更により、共通テストに集中する場合には、確率や数列といった定番分野に集中することが合格への近道となるでしょう。
効率的に学習を進めるには、過去問演習を軸に出題傾向をつかみ、図表化や思考過程の整理を習慣にすることを意識することが大切です。
不要な勉強を避け、必要な範囲を強化すれば、共通テストの数学でも安定した得点が期待できます。
2025年の共通テストから新課程により数学の出題範囲や試験内容に変更はあるものの、”簡単になった”、”難しくなった”というような変化はありません。
普段の学習から基礎を徹底し、合格を掴むための思考力を身につけましょう。