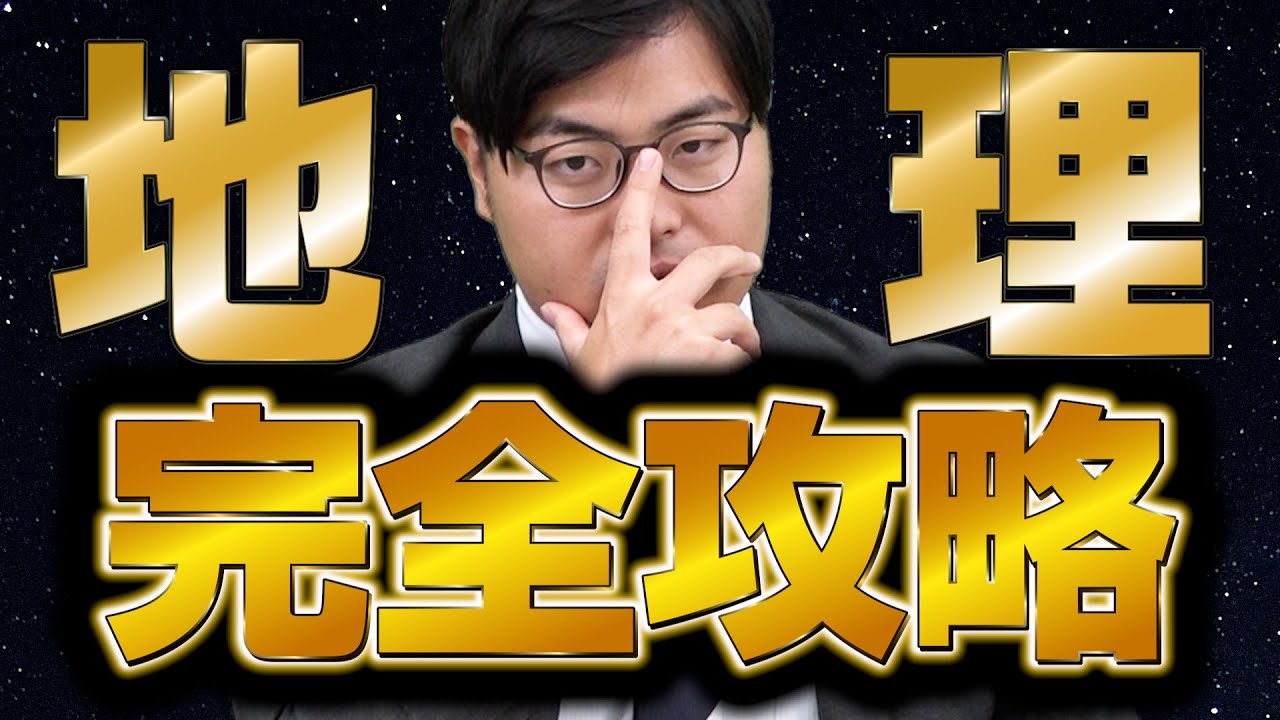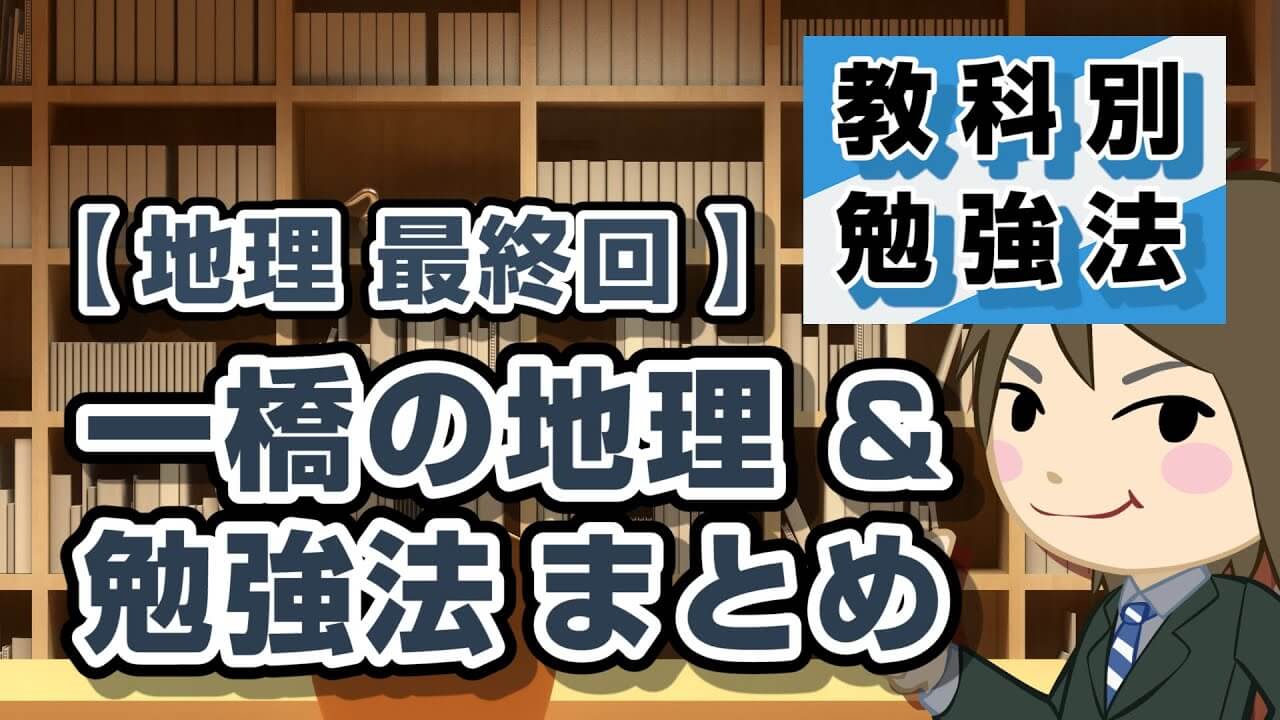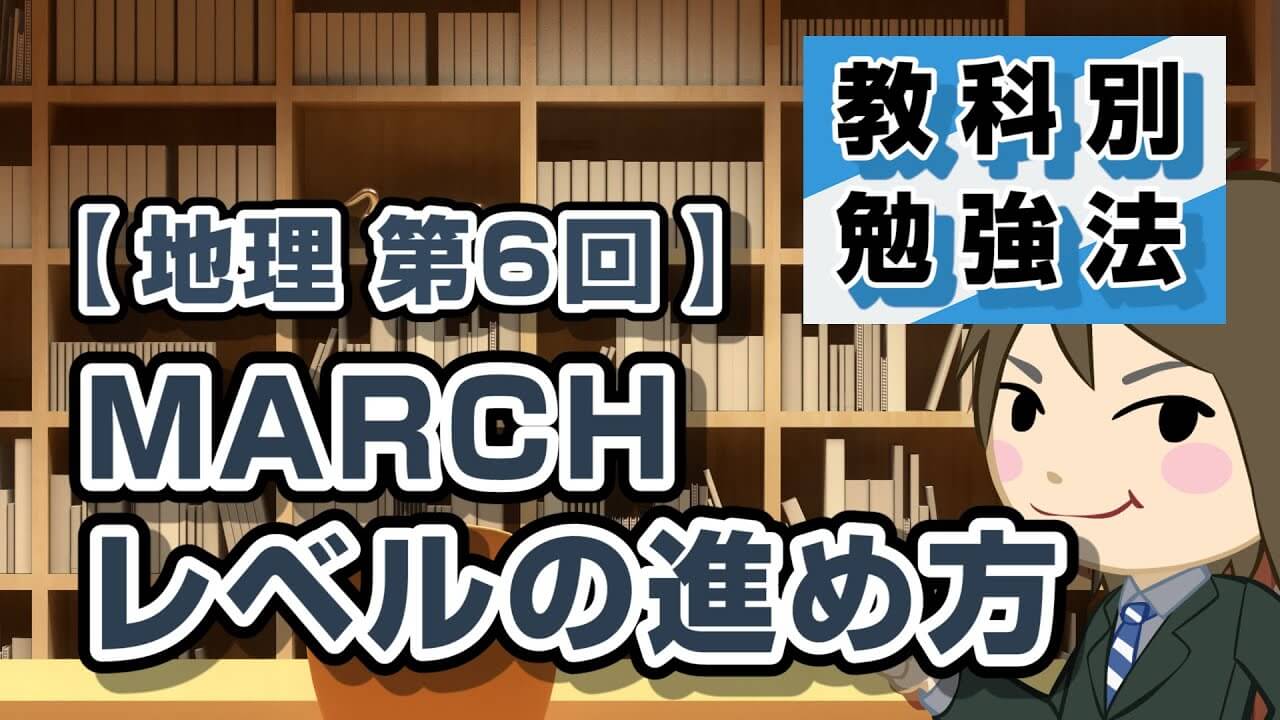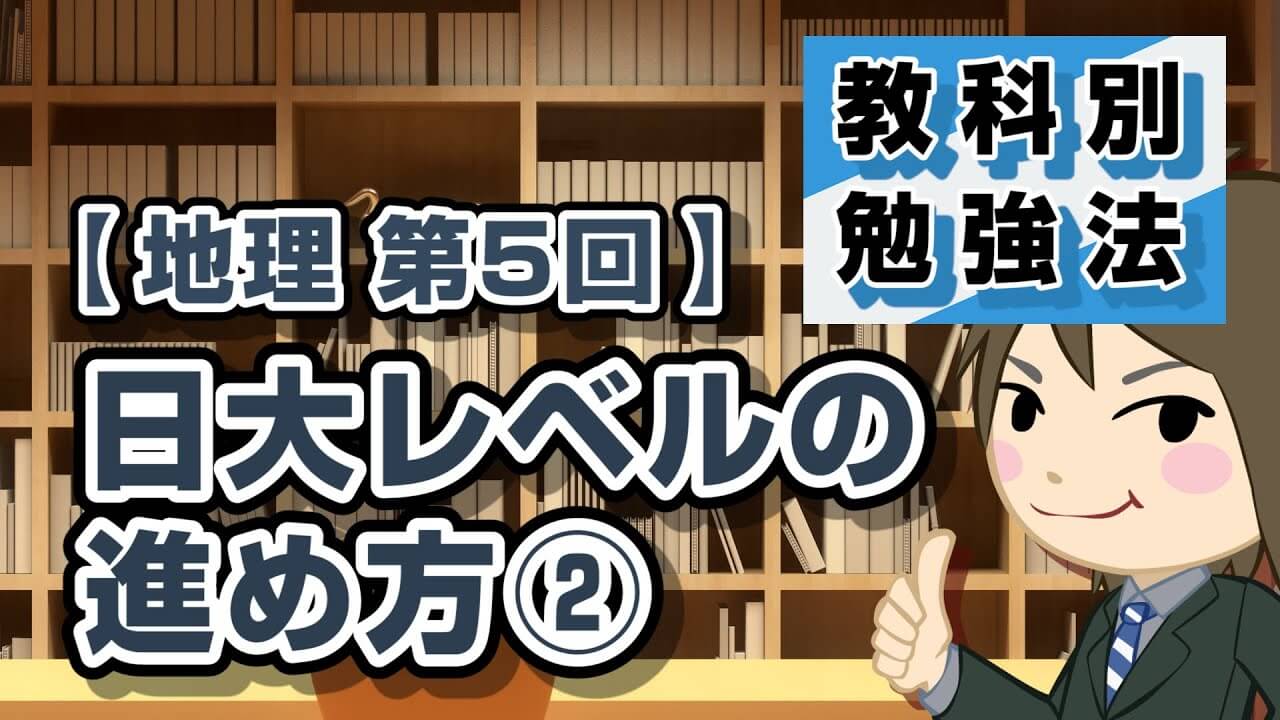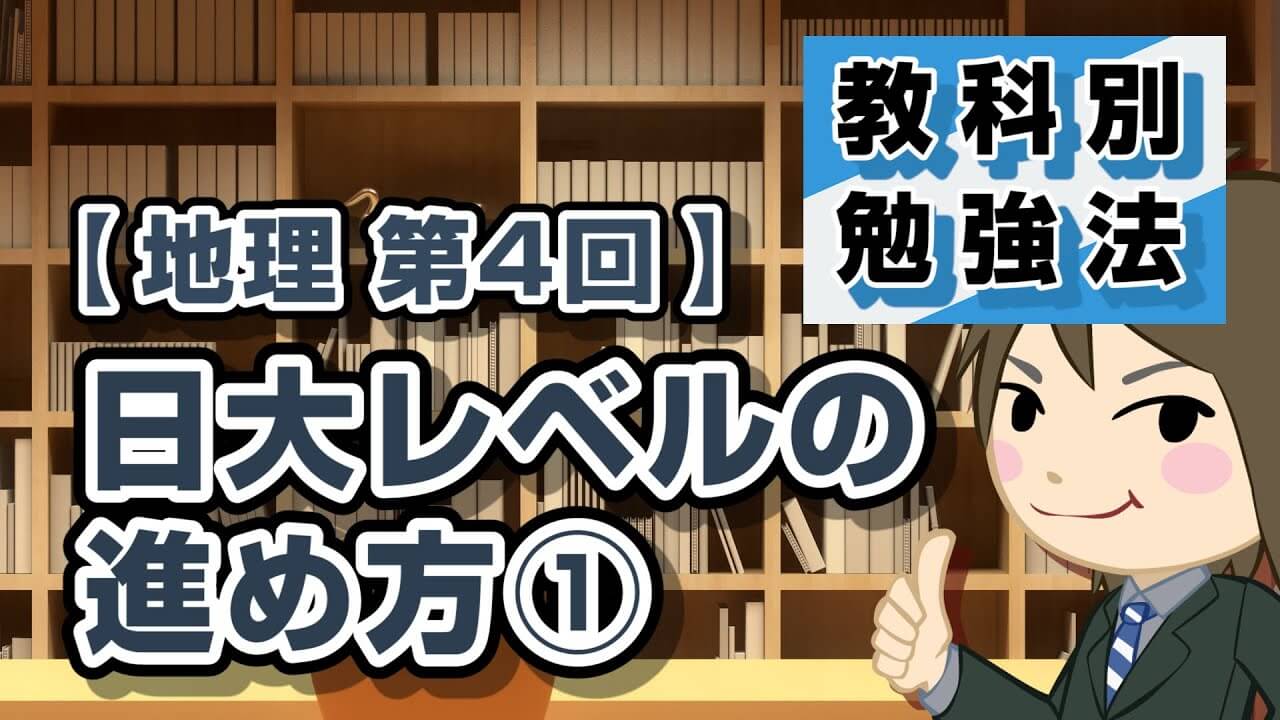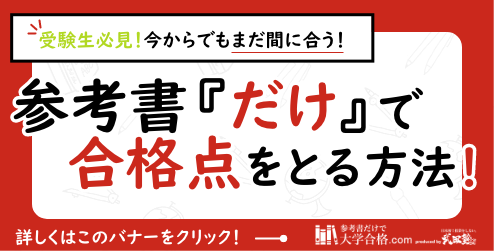地理で学ぶことは大きく分けて二つ
系統地理と地誌
系統地理というのは、テーマ史って思った方が分かりやすいでしょう。気候や地図、ジャンル毎に扱ったものです。地誌というのは国ごとにテーマを扱う。タテとヨコの違いのように考えると整理しやすいです。
どちらの分野から勉強をはじめれば?
1つの国について詳しく学びたければ、地誌からが良いと思います。他方で、例えば「貿易」など1つのテーマについて学びたければ系統地理からが良いでしょう。その場合は1つずつの分野を固めていって、1つの国のある分野について学んで、また別の分野は・・・・というように覚えていく必要があります。なので、どちらから始めればいいかとなると系統地理です。先にテーマごとに学んでいき、その後に地誌で1つの国ついて詳しく学んでいく進め方が良いでしょう。
地理の科目は何をしたらいいかわからない人が多い?
暗記だけでは得点にならない
地理っていう科目自体は、何をしたらいいのかがわからないっていう人がすごく多いです。なぜなら、覚えたからって解けるかというとそのような訳にもいかない事が多いです。だからって問題集をひたすらやっていけば力が着いていくのか、知識系の本を取り入れても知らない用語とかが問題集に沢山出てきます。そんな内に、これで大丈夫なのだろうか、という不安が多くあります。暗記は当然ありますが、覚えただけだと点にならない科目だという点に特徴があります。
がむしゃらにやれば何とかなる!訳ではないのが地理
正しい勉強方を身につける
地理は、問題の解き方や、情報の分析方法。またそれを元にした覚え方、学習方法というのが、自分自身の中に体系化されてないと、ただひたすらにがむしゃらに取り組んだから得点が上がるような科目ではないという点が難しいんです。
なので、分析力の部分があり、更に知識は必要ですが、その場で対応する能力が一番要求される科目であるという事です。ただ、その考え方さえ分かってれば、難しい訳ではありません。ただし、一橋を除きます。