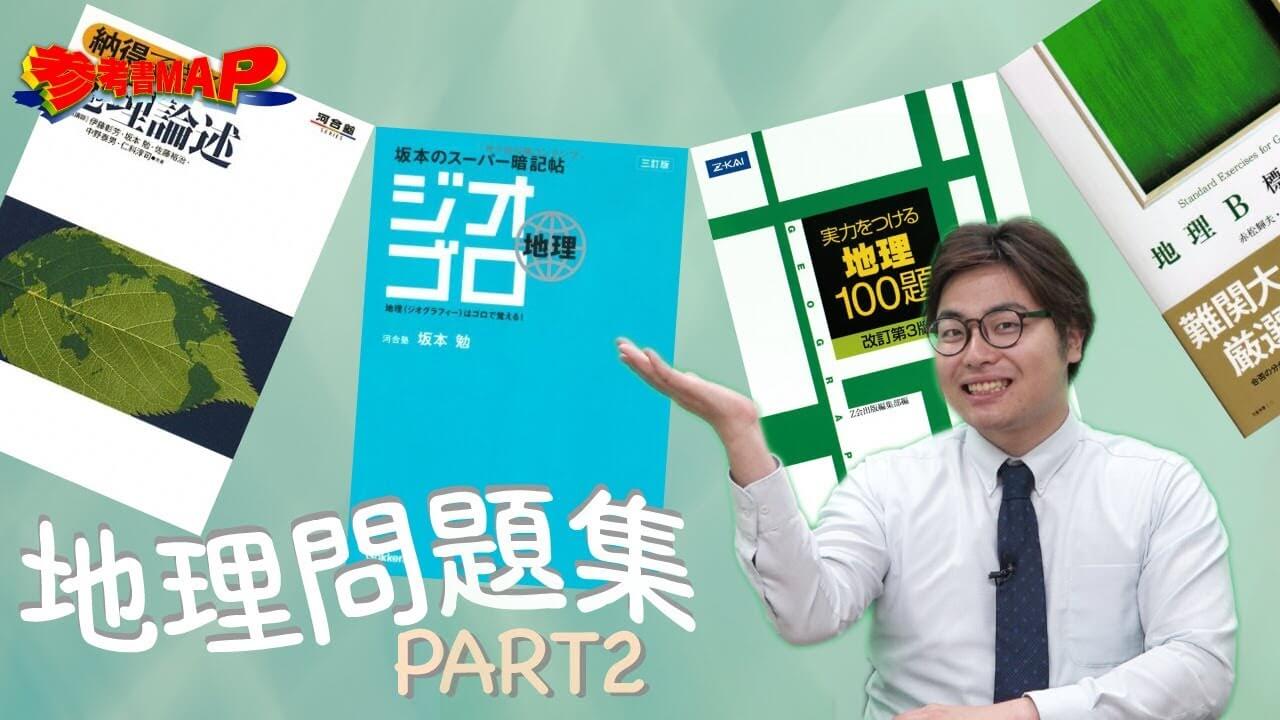今回は、地理の問題集の内、共通テストレベルまでに対応できるものをピックアップしてご紹介します。
入試の地理で高い点数を取るために、まずは今回紹介する問題集を使ってしっかりと基礎知識を固め、さらに上のレベルの問題にチャレンジするための土台を作ってください。
また、地理の問題の傾向も共にご紹介するので、地理の勉強に活用してみてください。
地理をマスターして志望校合格を目指しましょう。
地理の問題の傾向は2つある
実は、地理の問題には2パターンの傾向があります。
1つ目は暗記力が求められるタイプの問題で、もう1つは思考力が求められるタイプの問題です。
この2つの傾向に備えて問題集や参考書で対策する必要があります。
①暗記力が求められるタイプの問題
1つは、単純に地理の重要事項が覚えられているかどうかの暗記力が求められるタイプの問題です。
この場合、問題に対して適切な答えが思い出せれば解けるので、比較的得点しやすいといえるでしょう。
知識のインプットとアウトプットを繰返して頭に定着させていきましょう。
②思考力が求められるタイプの問題
そして2つ目は、思考力が求められるタイプの問題です。
この形式は、例えば共通テストのようにデータや表、グラフなどが与えられていて、そのデータをもとに今まで身につけた地理の知識を使って答えを考えるといったような問題が多く出題されます。
そのため、知識をただ暗記しているだけでは解くのが難しいです。
覚えた知識を活用して、どのように問題を解けばよいのか、どういった点に着目してデータを分析すればよいのかといったポイントを、実践的に学んでいく必要があります。
今回ご紹介するおすすめの問題集には、この2つのパターンそれぞれに対応できるものが含まれていますので、学習するときの参考にしてみてください。
地理を勉強する時のポイント
地理を勉強する時には押さえるべきポイントがあります。
ここからは地理を勉強する時のポイントを3つご紹介します。
地理の成績を上げたい人はぜひ参考にしてみて下さい。
アウトプットに力を入れる
地理を勉強する時のポイント1つ目は、アウトプットに力を入れることです。
共通テストの地理では統計やデータを見て答える問題なども出てきます。
そのような問題に対応するためには多くの演習量をこなし、アウトプットを繰返して知識を応用させる力を身につけることが有効です。
地図を見ながら勉強する
地理を勉強する時のポイント2つ目は、地図を見ながら覚えることです。
地理を勉強する時に地図を見て勉強すると、河川や標高などからその国の気候や環境等が分かります。
知識を丸暗記するのではなく、様々な情報を繋ぎ合わせて覚えるためにも地図を見ながら勉強するようにしましょう。
背景も合わせて覚える
地理を勉強する時のポイント3つ目は、背景も合わせて覚えることです。
共通テストの地理では、ただ知識を暗記しただけでは解くことができない問題が出てきます。
知識を応用させる前段階として、その知識の背景情報を合わせて覚えておくことが重要です。
使用する地理の参考書と大まかな勉強法
-
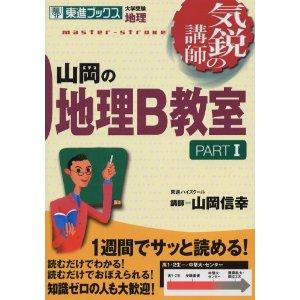
① 山岡の地理B教室 PART1.2
【特徴】
この参考書は地理の知識を詳しく解説した講義系参考書です。
地理の知識をただ暗記させるだけで終わらせず、どうしてそうなるのか「考え方」にフォーカスした内容になっているので内容が頭に入ってきやすいです。
地理を暗記が苦手だと思っている人のオススメしたい1冊です。
【使い方】
この参考書では地理の基本部分を理解していきましょう。
使い方としては、本文を読んだ上でテキスト部分の赤字を覚えるのが基本ですが、問題自体が非常に少ないので、その用語を覚えただけではあまり意味はありません。
知識の習得は今後の参考書がメインとなるので、この参考書では地理でどんなことをやっていくのかを学習しておきましょう。
-
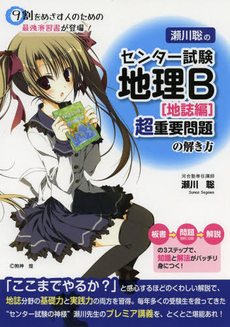
② 瀬川聡の共通テスト地理B(系統地理編)
【特徴】
この参考書は、地理学習の土台である自然環境、産業、民族問題、都市問題などの諸課題、環境問題などの地球的課題といった系統地理分野を扱っている問題集です。
知識を確認する部分と問題演習をする部分の両方が掲載されているので、知識のインプットとアウトプットが一気に行えます。
効率的に学習を進めたい方におすすめな1冊です。
【使い方】
本参考書を使用する上で最も重要なのは、解説を読み込んで分布やデータ等の理由を理解することです。
また「地図帳をチェックしよう!」の部分では必ず地図帳を参照して理解を深めましょう。
本文の理解が出来たら別冊の問題集で演習を行い、すべての選択肢の正誤理由が応えられるようになるまで復習を行います。
また、参考書を読むときはかならず該当地域の地図帳をひろげて確認する癖をつけましょう。
センターで8割以上を目指す人はこの参考書に加え、各予備校のマーク式予想問題集やセンター過去問で演習を行ってください。
-

③ 共通テスト過去問 本試
【特徴】
この参考書は共通テストの過去問や試行調査問題を計10回分収録しています。
また、逆引き学習に使える過去問INDEXがついているので自分の弱点の問題を選んで問題を解くこともできます。
共通テスト対策を万全に行いたい人におすすめです。
【使い方】
目標は85%から90%くらいに設定して、「間違えた問題」「正解したが自信がない問題」はテキスト(瀬川聡の共通テスト地理B[系統地理編]超重要問題の解き方)に戻って確認し、インプットのやり直しをおこなってください。
常に「各時代のどの部分が得意か?又は不得意か?」を意識して演習・復習に取り組みましょう。
-

④ 2015年マーク総合問題集
【特徴】
河合の模試の過去問をまとめた問題集です。
難易度は共通テストの標準的な難易度に近いため、過去問が一通り終わったらまず最初に解いておきましょう。
通常の過去問に比べて解説が充実しているので、よく読むようにすると良いでしょう。
【使い方】
使い方は共通テストの過去問と同じで構いませんが、過去問の後にやるため、過去問でやったことができているようになっているかを確認しながら解いていきましょう。
詳しい解説が付いているので、読むだけではなく、どうしたらその解答に至れたか、思考プロセスについても考えながらやるとよいでしょう。
分からないところが無くなるくらい繰返し使用しましょう。
-

⑤ 2025年用共通テスト 実践模試 地理
【特徴】
Z会の模試に加え、予想問題が1回分入っている問題集です。
共通テスト対策の中でも難易度は高めで仕上げに使いましょう。
また、解説が充実しているので、間違えた問題はしっかり復習することができる点も魅力の1つです。
【使い方】
解説もかなり詳しいですが、ある程度点数が取れる状態まで仕上げておかないと使いこなせない可能性が高いです。
基礎知識はきっちり終えたうえで入るようにしましょう。
この問題集に入る時点で、点数が7〜8割程度取れていないようであれば、ここまでにやった参考書に戻って仕上げなおしておきましょう。
-

⑥共通テストへの道 地理
【特徴】
『共通テストの道』は解説がシンプルにまとまっている参考書です。
共通テストの出題のねらいや対策方法などが載っているので、共通テスト対策をしたい人にうってつけです。
また、単元別になっているので苦手な単元を重点的に勉強することができます。
【使い方】
『共通テストの道』は共通テストの過去問を単元別に再編成されているので、特に苦手な単元がある人は重点的にその単元を勉強しましょう。
また、解説では間違えやすいポイントを解説しているので、しっかりと読んで対策すると良いです。
問題量が多いのでこの1冊を完璧にして演習量を重ねていきましょう。
-
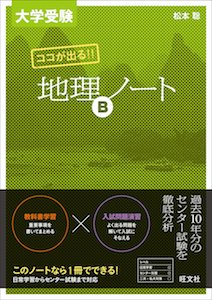
⑦地理Bノート
【特徴】
この教材は、先ほどの2パターンで言うと「暗記系」の教材になります。
覚えておくべき地理の基礎知識がまとまっているので、この教材を1冊しっかりしあげることで、地理で必要な知識を一通り覚えられるのが特長です。
地理で覚えるべき暗記事項の分量は、日本史や世界史に比べると少ない方ですが、やはり最低限の暗記は必要になる科目です。
これから地理を学習する人や、授業は一通り受けたけれど基礎知識を改めて整理したいという人は『地理Bノート』を使って暗記を進めていくことをおすすめします。
【使い方】
空欄補充形式の参考書となっているので直接は書き込まずに、別の紙に書くことで繰返し使うことできます。
もしくは、赤字で答えを記入して赤シートで隠しながら進めても繰返し使うことができるでしょう。
インプット用としては不足している部分もあるので講義系参考書と併用して使うのが良いです。
-
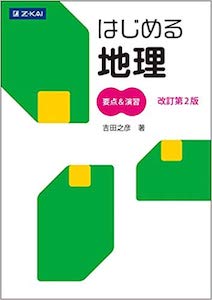
⑧はじめる地理
【特徴】
この参考書は、地理の基礎的な知識をコンパクトにまとめた参考書です。
要点確認の部分と空所補充の部分が両方あるので知識のインプットとアウトプットを同時に行うことができます。
知識のアウトプットをしながら基本が覚えられているかどうかを確認し、穴をふさいでいきたいという人は『はじめる地理』を使って復習していくと、学習効果が高まります。
【使い方】
要点確認の部分を読んで知識をインプットしましょう。
その後、空所補充の部分に取り組んで知識のアウトプットをしていきましょう。
繰返し使うことによって知識が定着するので、空所補充は別の紙に書くか、赤字で埋めていくことをおすすめします。
地理のおすすめ参考書|まとめ
今回、共通テストレベルの地理の参考書をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
地理の問題の傾向は2つあり、暗記力と思考力が問われる問題が出てきます。
そのため、参考書や問題集でその2つを鍛える必要があります。
今回ご紹介した参考書を使って、地理の成績を上げていきましょう。