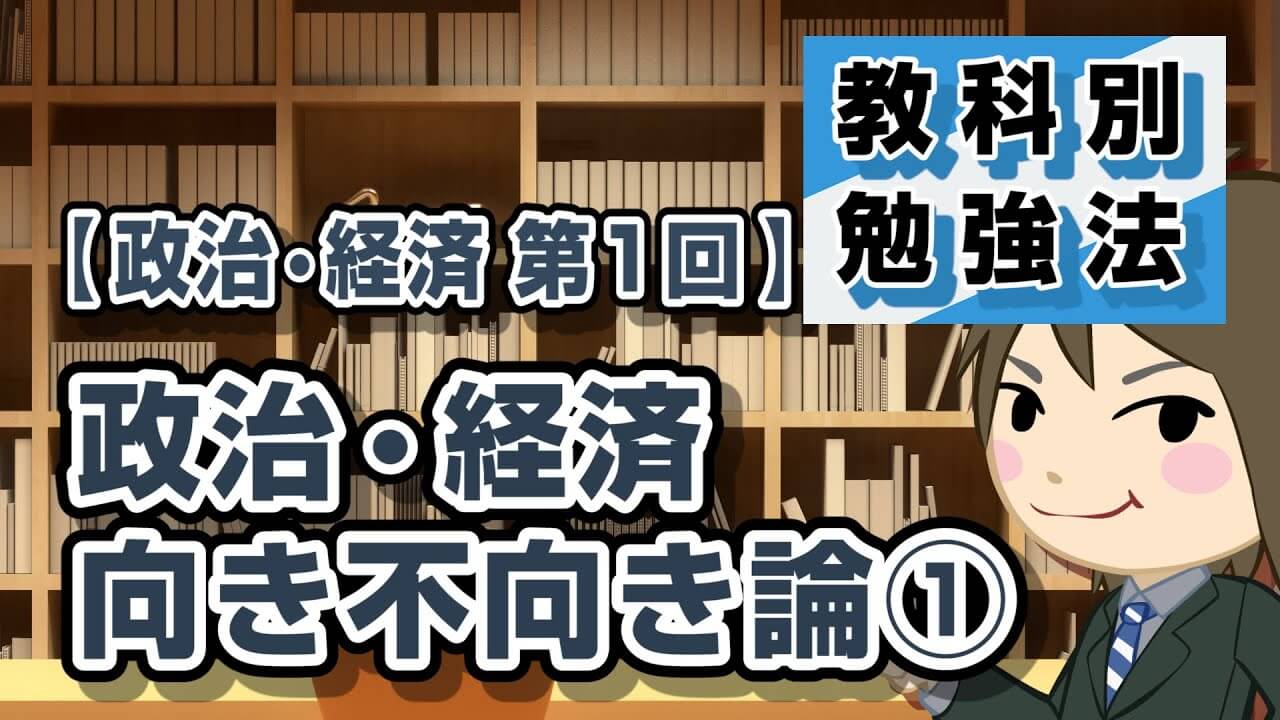「政治経済が苦手…」「共通テストの時間が足りない…」そんな悩み抱えていませんか?
共通テストの政治経済は、日本史や世界史などの暗記科目よりも比較的量が少ないですが、細かなとこまで理解を求める問題が多いです。
問題の出題傾向と出題範囲を把握し、自分に合った勉強方法を取り入れることで政治経済の点数を伸ばすことができます。
そこで、今回は共通テストで政治経済6割、8割を達成する方法を紹介します。
共通テストの政治経済科目について
共通テストは2025年から新課程が始まり、6教科30科目から、7教科21科目に変更されました。
新課程の公民科目では、「公共、倫理」、「公共、政治経済」か「地理総合/歴史総合/公共」3つの内どれか1つを選択します。
この変更により、共通テストの政治経済科目にも変更された点があるのでしょうか?
新課程の政治経済はどうなってるの?
これまで、高校の公民科では現代社会が必修でしたが2022年度から廃止され、代わりに公共が新設されました。
公共は、社会の仕組みや現代社会の仕組みを深く理解し、社会とかかわるための知識と能力を育むことを目的とした科目です。
2025年度の共通テストから公共教科が導入され、「公民・政治経済」では公共から25点、政治経済75点それぞれ出題されました。
よって、次年度からも同様に政治経済の配点は75点と想定されます。
公共は、政治経済と倫理、両方に重なる部分がある科目です。一般に政治経済の方が重なる部分が多いとされ、「公共、政治経済」を選択したほうが比較的に勉強量は少ないと言えます。
政治経済の内容
共通テストの政治経済は、政治・経済・国際関係など様々なテーマを扱い、これらの情報を組み合わせながら問題を解いていきます。
近年の試験傾向として、思考問題が増えたことがあげられます。新課程の公民科目は、マーク数が減り、資料やデータを読みとき考察する問題が増えている傾向があります。
基礎知識にプラスして思考力が求められる教科と言えそうです。
政治経済の特徴
新課程の共通テスト公共、政治経済は、従来の共通テスト政治経済の範囲と大きな変更はありません。
そのため、従来の共通テストの勉強法や対策をしっかり行うことが目標得点獲得のカギになります。
政治経済の特徴をつかんで高得点を狙っていきましょう。
出題傾向
共通テストの政治経済では、ある特定の分野から集中的に出題されることはなく、政治経済のあらゆる分野からまんべんなく出題されます。
また、各分野を掛け合わせた問題が出題されるケースもあるので注意が必要です。
政治経済の問題の傾向として、資料の読み取り問題や会話文での出題がみられ、憲法の条文比較・図解や国債発行額の推移グラフなど様々な資料を扱います。
このように、資料から読み取ったことと、自分の持っている知識を組み合わせて解答を導き出す、パズル的な思考を求められます。
また、計算問題や時事的な問題を絡めてくる場合もあるので、過去問などを活用しながら出題傾向を理解していくことが大切です。
暗記+αが求められる
共通テストの政治経済科目では、高校の政治経済教科書で扱われる分野すべてが出題範囲であり、主に政治、経済、国際関係の3つの分野から問われます。
政治経済は歴史科目ではないため、暗記量は少なく、出てくる用語も実生活で一度は耳にしたことがある単語が出てくるので、暗記にそこまでの抵抗は感じないかもしれません。
しかし、共通テストでは一問一答のような単純な知識問題はほとんど見られず、暗記した知識を使った資料の読み取りや、グラフの解析などの思考力や時事問題に対する理解を求める問題が出題されます。
単位用語を覚えるのではなく、背景・仕組み・つながりを図や文章で理解する必要があります。
時事問題の比重が重い
共通テストの政治経済は、他の社会科目に比べて、今起きていることに関する問題が多く出題されます。
2024年度の政治経済では新型コロナ渦の影響を考慮するなどの時事的な話題が目立ちました。
近年起こった問題や変化だけでなく、今年度起こったことにもアンテナを張っておくことが重要です。
新聞や時事問題集(特に秋以降)を使って最新の用語やテーマを抑える必要があります。
比較的短期間で点数アップが狙える
共通テストの政治経済は、現代的な内容が多く「理解→演習」の流れをしっかり作れれば短期間で点数アップが狙いやすいです。
政治経済は、知識だけでなく思考力や時事問題に対する理解を問いてきます。
逆にいうと、たとえ知識がなくても思考力さえあれば選択肢を絞り込むことできるため暗記が苦手な人や現代の社会問題に関心がある人におすすめです。
過去問や模試などで出題の傾向に慣れておくのが良いでしょう。
共通テストの政治経済で6割に届かない原因と勉強法
「共通テストの政治経済で6割しか点数が取れない。」という人にはそれぞれ原因があります。
まずはその原因を突き止めることで、6割を突破を目指していきましょう。
ここでは、点数がなかなか取れない原因について解説しながら、対策方法として「勉強法」をご紹介していきます。
苦手な箇所を見つけ、自分に合った勉強方法を取り入れていきましょう。
用語の理解不足
「○○とは何か?」という問いや選択肢の意味が取れない場合、シンプルに知識が足りていないケースが多いです。
教科書や参考書を読み流していて、重要語句の定義や背景を理解できていない可能性があります。
身近な内容で覚えやすいとはいえ、単に単語を理解していても点数アップは見込めません。
時事に絡む問題で得点するためにも時事的な背景を意識して、単語の意味を確認していきましょう。
勉強法
政治経済を0から取り組む場合、まずは教科書や参考書の知識や原理を全範囲理解する必要があります。
似たような単語が多いため、違いを1つ1つ確認しながら行うと良いでしょう。
その際、用語の意味を理解しながら背景も一緒に暗記することが重要です。
それぞれのつながりを意識することで、忘れることを防ぐと同時に、応用問題で覚えた知識を活かすことができます。
「政治分野のこの制度は、経済分野でこういうことが起こったからか!」といった感じです。
このような勉強法を取れば、パズルのピースが組み合わさって行くように、楽しく学習できます。
論理的な文章の読解が苦手
共通テストの政治経済問題で多いのが、選択肢の違いが分からず、なんとなく選んで外すといったパターンです。
政治経済の問題は論理的に書かれており、選択肢も同様に、1文1文が長く複雑に書かれています。
説明文形式が多く、語句暗記だけでは対応できません。
テーマを表す文章を見つけ、文章の大枠をつかむことが重要です。
勉強法
演習問題をたくさん解いて出題形式に慣れましょう。
「知識が完璧に身についていないから、演習問題にまだ取り組まない。」といった受験生は非常に多いです。
結局のところ、点数を取ることが目的ですから、ある程度知識がついた段階ですぐに演習問題に取り組んだ方が良いでしょう。
知識をたくさんインプットしても、それをうまく活用できなければ点数アップは見込めません。
演習問題をたくさん解いて出題傾向をつかみ、自分の苦手分野を潰していきましょう。
計算・統計グラフ問題が苦手
GDP、物価指数、税率、国際収支などグラフを扱う問題が出題される傾向は高いです。
グラフ問題では、まずグラフの基本構造を見る癖をつけることが大切です。
データの見方として以下のポイントを抑えると良いでしょう。
- 出典・タイトルを確認し、何についてのグラフか把握
- 縦軸・横軸の単位は(円、%、人、年)の何か目を通す
- 最大値・最小値・変化の向きをざっくりつかむ
基本的にピーク値や変化が大きいところが問題になりますので、そこだけ注目すればいいです。
また、問題文とグラフがつながらない場合、問題文の指示に従って該当範囲のみ見るようにしてください。
例えば、「AはBより多い」と合った場合AとBのバーを比較、「この翌年にかけて上昇」とあれば2年分の傾きを確認するなど該当箇所を見極めていきましょう。
勉強法
グラフ問題は難しく感じるかもしれませんが、それぞれいくつかのパターンがあります。
問題によってそれぞれ異なるように見えますが、解き方のパターンさえ理解していれば、簡単に選択肢を絞り込めます。
グラフ問題は、むしろ特別な知識は必要なく、数学のグラフ問題と同様に考えて良いです。
計算ミスに注意し、解き方のパターンを覚えれば安定して得点できます。
共通テストの政治経済で8割に届かない原因と勉強法
政治経済の場合、6割まではいけても8割を超える点数を取ることはとても難しいです。
理由として、正誤の判断基準が他の社会科目と比べて問題文がややこしいこと、政治と経済でそれぞれ解き方が違うこと、時事問題などの対策が必要なことがあげられます。
ただし、応用や時事の理解度さえあれば十分得点を得られる科目でもありますので、政治経済科目に抵抗がない場合にはこれらのポイントについても乗り越えるよう頑張ってみましょう。
現代の経済・政治時事の理解不足
共通テストの政治経済問題を解くにあたって避けては通れないのが時事問題です。
時事問題は、社会で起こった出来事と教科書から学んだことを関連付けて出題されることがほとんどのため、ただ暗記してもいい点数は見込めません。
また、毎年、新しい情報を入手する必要があります。
時事問題で落としやすい分野としては、受験生の手がまわらない外交や保安問題、また国際経済の分野などが挙げられます。
「難しそうだし、めんどくさいから時事は捨てよう。」そう思うかもしれません。
しかし、これは他の受験生も同じことです。
ここを抑えることができれば他のライバルに大きな差をつけることができるでしょう。
勉強休憩の隙間時間にニュースをチェックしたり、朝新聞の一面だけ読んで登校するなど毎日少しでも情報に触れることが大切です。
勉強法
時事問題は、知識問題というより「ニュース問題の背景」と「制度の理解」が組み合わさって出題されます。
出題テーマの理解と関連知識をどれだけ広げているかがカギになってきます。
どれも完全なニュース問題ではなく、教科書の内容+最新動向となっているため教科書以外の部分は自分で埋めなければなりません。
勉強方法として、自分の気になる事柄やニュースをテーマ別にまとめたプリントを自作することをおすすめします。
気になるニュースがないという方は、AIを使って共通テストに出そうな内容を検索できます。
作ったプリントをもとに、AIを使って共通テストに出そうな時事問題を作成し、問題を解き自分がどこまで理解してニュースを読めているかなどを定期的に確かめると良いでしょう。
問題を解くにあたって、ただ正解、不正解を確認するだけでなく、なぜあっていたのか、違う選択肢はどこが違ったのか、一つ一つ言語化できることが大切です。
解説を読み込み、関連知識をどんどん吸収することが時事問題攻略のカギです。
時間が足りない
共通テストの政治経済問題は説明形式の記載が多く、特に文字数が多いです。
そのため、問題を解く時間が足りず結果的に点数を落としてしまうという受験者も少なくありません。
また、資料から必要な情報を抜き取る作業やグラフから読み取った数値を使って計算を行うなど、とにかく時間がかかります。
初見の問題では確実に時間を取られてしまうため、演習問題をたくさん解いてテストまでに雰囲気や問題の傾向をつかんでおく必要があります。
また、用語の定義は分かっているのに、選択肢の消去がうまくできない場合もあります。
選択肢には、紛らわしい言い回しが使われどれも正しいように見えます。
これらは出題傾向を覚えることで、時間を削減していきましょう。
「すべて、必ず、常に、唯一」などの強調表現がある場合、正しいことでも例外があると誤りになります。強い断定表現や、一見、正しそうな常識表現には注意が必要です。
さらに、「名目GDPと実質GDP」や「公債と国債」など似た言葉は混同しやすいです。
類似用語の違いを説明できるかを意識して暗記していきましょう。
勉強法
過去問をたくさん解いて、政治経済問題に対する嗅覚を研ぎ澄ませていきましょう。
問題の出題形式に慣らしていき、苦手分野に時間を使えるよう、ペース配分が重要です。
時間配分は過去問や模試で似たような問題を解くことで、どれだけ時間がかかるか逆算できます。
共通テストは毎年のように変更や改定が行われていますが、3~5年分の過去問であれば十分活用できます。
ただし、「政治経済」の性質上、時事問題があり、あまりに古い問題になると、法改正がされ現在と解答が異なる場合があります。
政治経済の過去問を解く場合、点数にフォーカスするのではなく、テストの問題形式に慣れることに意識してみてください。
共通テストで政治経済6割、8割突破するための勉強法 | まとめ
今回は、共通テスト政治経済のおすすめの勉強法をご紹介しました。
政治経済はその名の通り、日本の政治や経済について出題されます。
暗記量が日本史や世界史に比べ少ないため、他の科目と異なり、高校3年生から受験勉強を始めても遅くはないでしょう。
政治経済は時事問題があるため教科書や参考書だけではなく、新聞を読んだりテレビニュースを見たりして勉強するのもおすすめです。
現代の社会情勢や政治について知識を付けられるので、興味を持つきっかけになるでしょう。
ただの試験科目として取り組むのではなく、自分の価値観を広げてくれるものとしてとらえることで、より楽しく勉強に取り組むことができるでしょう。