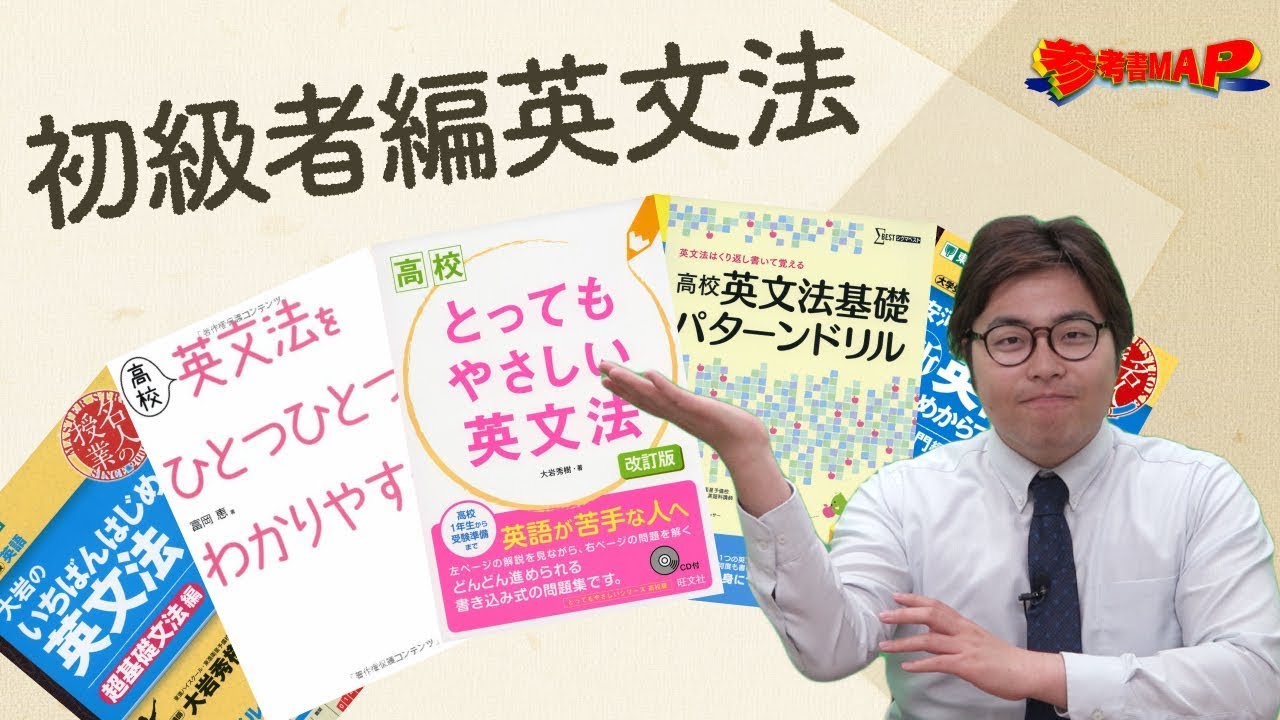今回ご紹介するのは、英語のリスニング対策用の教材4冊です。
共通テスト対策から東大の2次試験対策まで、幅広いレベルの参考書をご紹介します。
リスニングは参考書で対策できるのか疑問に思う人もいるかもしれませんが、リスニングの問題は大学によって傾向があるため、出題パターンを参考書で学んでおけばしっかりと得点アップにつながります。
もちろん、基本となる英語の聞き取り能力自体は必須となりますが、その上で各大学の出題傾向をつかんでリスニングの問題に慣れておくと高得点が見込めます。
リスニングを上達させるコツ
リスニングはただ何度も音源を聞いていれば上達するものではありません。
そこで、ここからはリスニングを上達させるコツを5つ紹介します。
リスニングの点数を伸ばしたいと考えている人はぜひ参考にしてみて下さい。
日本語に訳さず英語のまま理解する
リスニングを上達させるコツの1つ目は日本語に訳さず英語のまま理解するという点です。
聞こえてきた英語を日本語に変換していると話されているスピードについていけなくなります。
そのため、聞こえてきた英語の風景や状況をそのままイメージすることが重要です。
分からない単語を調べる
リスニングを上達させるコツの2つ目は、分からない単語を調べることです。
リスニングの中で出てきた分からない単語は聞き取ることが難しいです。
そのため、分からない単語が出てきたら逐一調べ、音声などで発音もチェックするようにしましょう。
スクリプトが付いている教材を使う
リスニングを上達させるコツの3つ目は、スクリプトが付いている教材を使うことです。
スクリプトが付いていない教材で勉強すると、聞き取れなかった単語が出てきた時に特定することができません。
また、聞こえてきた英語を紙に書きとるディクテーションの答え合わせなどにも使うことができるので、必ずスクリプトが付いている教材を選ぶようにしましょう。
自分のレベルと合致している教材を使う
どの科目にも言えることですが、自分のレベルと合っている参考書を使うことは極めて重要です。
自分のレベルとかけ離れている参考書を使うと、全然聞き取れないなんてことが起こってしまう可能性があります。
そのため、全然聞き取れなかった場合は参考書のレベルを下げて取り組むことをおすすめします。
リスニングの勉強を習慣化する
リスニングを上達させるコツの5つ目は、リスニングの勉強を習慣化することです。
リスニングの勉強は後回しにしてしまいがちですが、少しやっただけで上達する科目ではありません。
そのため、日々の勉強習慣の中に取り入れて英語を聞き慣れる必要があります。
できれば毎日英語を聞く時間を作ると良いでしょう。
共通テストレベルから東大対策まで!リスニングのおすすめ教材4冊
今回ご紹介する4冊の教材は、主に各大学の出題傾向に合わせた対策ができる参考書です。
基本となる英語のリスニング力の強化には、『速読英熟語』などCD付の例文集をシャドウイングすることをおすすめします。
本文を暗唱できるくらいまで繰り返しCDのシャドウイングを行い、英語のフレーズを聞き取る基礎力を身につけることが大切です。
その上で、今回ご紹介する教材のような各大学別の対策問題集を学習すれば、リスニング対策は万全になります。それぞれの教材について詳しく見ていきましょう。
共通テストのリスニング対策におすすめ!『共通テストのツボ 英語リスニング』

最初にご紹介するのは、共通テストのリスニング対策におすすめの『共通テストのツボ 英語リスニング』です。
易しい問題が収録されている
この教材では、共通テストの出題傾向に合わせて、やさしめの問題が収録されています。
解説はかなり分かりやすいため、リスニングの問題が解けずに悩んでいる人でも問題なく学習が進められます。
リスニング対策の入門としてもおすすめなので、問題を解くためのリスニング力を鍛えたい人はまず『共通テストのツボ 英語リスニング』から取り組んでみてください。
解説が分かりやすい
また、リスニングの問題で放送される英文は、いつでも100%完璧に聞き取れるとは限りません。
そんな時、問題に答えるために必要不可欠な部分だけは最低限聞き取ることが大切になります。
『共通テストのツボ 英語リスニング』は、最低限の箇所を把握するために聞いておくべき注意ポイントも解説されているのが特長です。
ある程度英語の聞き取り能力が身に付いた段階でこの問題集に取り組むことで、リスニングの点数を取るためにどのような聞き方をすればよいのかが把握できるようになります。
私大の一般入試や国公立2次試験のリスニング対策なら『関 正生の英語リスニング プラチナルール』

次にご紹介する『関 正生の英語リスニング プラチナルール』は、私立大学の一般入試や国公立大学の二次試験対策におすすめのリスニング教材です。
レベルの高い問題集
『関 正生の英語リスニング プラチナルール』は、ある程度レベルの高いリスニングの問題にも対応できる問題集となっています。
解説が丁寧で分かりやすいため、リスニングの点数で伸び悩んでいる人にもおすすめの教材です。
『関 正生の英語リスニング プラチナルール』を使って、リスニングを得点源にできるだけの力を身につけましょう。
テクニックが書かれている
英語のリスニングでよく聞かれる質問パターンについて、どのような質問文が聞こえてきたら何を想定しておくべきか?など、解くための戦略やテクニックが事細かに解説されています。
さらに、リスニングでよく出てくる英語のフレーズや表現のパターンが知識としてまとまっている点も、『関 正生の英語リスニング プラチナルール』の特長です。
リスニングで出てくる英語表現は、文法・語法問題で頻出の表現とは少し異なります。
また、文字で書いてあれば意味が読み取れる表現でも、リスニング問題として聞き取るとなると難しいものが多いです。
そこで、『関 正生の英語リスニング プラチナルール』に載っているリスニングで頻出の表現を頭に入れておくことが大事になります。
聞き取りが難しい表現は基本となるリスニング力が高くても意味が分からないという人が多いので、しっかり対策しておくことでほかの受験生に差をつけることが可能です。
東大のリスニング対策をするなら『灘高キムタツの東大英語リスニング』と『キムタツの東大英語リスニングスーパー』の2冊がおすすめ
最後にご紹介するのは、東大のリスニング対策に特化した教材です。
難関大の対策にピッタリ
これらの教材は、東大のリスニング問題に即した形で構成されていますが、東京外語大学やICUなどの東大以外の英語の難関大学を受験する人にも役立ちます。
ハイレベルな問題までカバーしていますが、解説も分かりやすいので問題なく理解を深めていける教材です。
特に、『キムタツの東大英語リスニングsuper』のCDは本番のリスニング試験対策として工夫されていて、机が動く音などの雑音が含まれているなど少し変わった教材になっています。
東大をはじめとする英語が難しい大学を受ける人は、『灘高キムタツの東大英語リスニング』と『キムタツの東大英語リスニングsuper』の2冊に取り組むのがおすすめです。
リスニングの勉強法
ここからは効果的なリスニングの勉強法についてご紹介していきます。
リスニング力を上げていきたい人は参考にしてみてくださいね。
問題集を繰返し解く
リスニングのおすすめ勉強法1つ目は問題集を繰返し解くことです。
繰返しとくことで次第に聞き取れなかった箇所が聞き取れるようになるでしょう。
1つの問題集につき3周ほどすればリスニングの力を上げていくことができます。
知らない単語や表現を書き留めて調べる
リスニングのおすすめ勉強法2つ目は知らない単語や表現を書き留めておいて調べることです。
リスニングの中で知らない単語が出てきた場合、聞き取ることは難しい上、何を言っているのか掴みにくくなりますよね。
そういった時は知らない単語を書き留めておき、調べるようにしましょう。
そうすることで語彙が増え、リスニングの問題に対応していくことができます。
シャドーイングをする
リスニングのおすすめ勉強法3つ目はシャドーイングをすることです。
シャドーイングとは音源を聞いて追いかけるように発音していく勉強法のことです。
自分で発音したことが無い単語は聞き取ることが難しいです。
そのため、実際に声に出して発音することで結果的にリスニング力が向上していくでしょう。
まとめ
今回は、英語のリスニング対策におすすめの4冊の教材をご紹介しました。
共通テストレベルの簡単なところから対策したい人には『共通テストのツボ 英語リスニング』がおすすめです。
私立大学や国公立の2次試験対策には『関 正生の英語リスニング プラチナルール』を学習しましょう。
そして、東大や外語大学、ICUなどの難関校のリスニング対策には『灘高キムタツの東大英語リスニング』と『キムタツの東大英語リスニングsuper』の2冊がおすすめです。
今回ご紹介したリスニングの対策教材を使って、志望する大学のリスニングの難易度に合わせた対策を進めていってください。