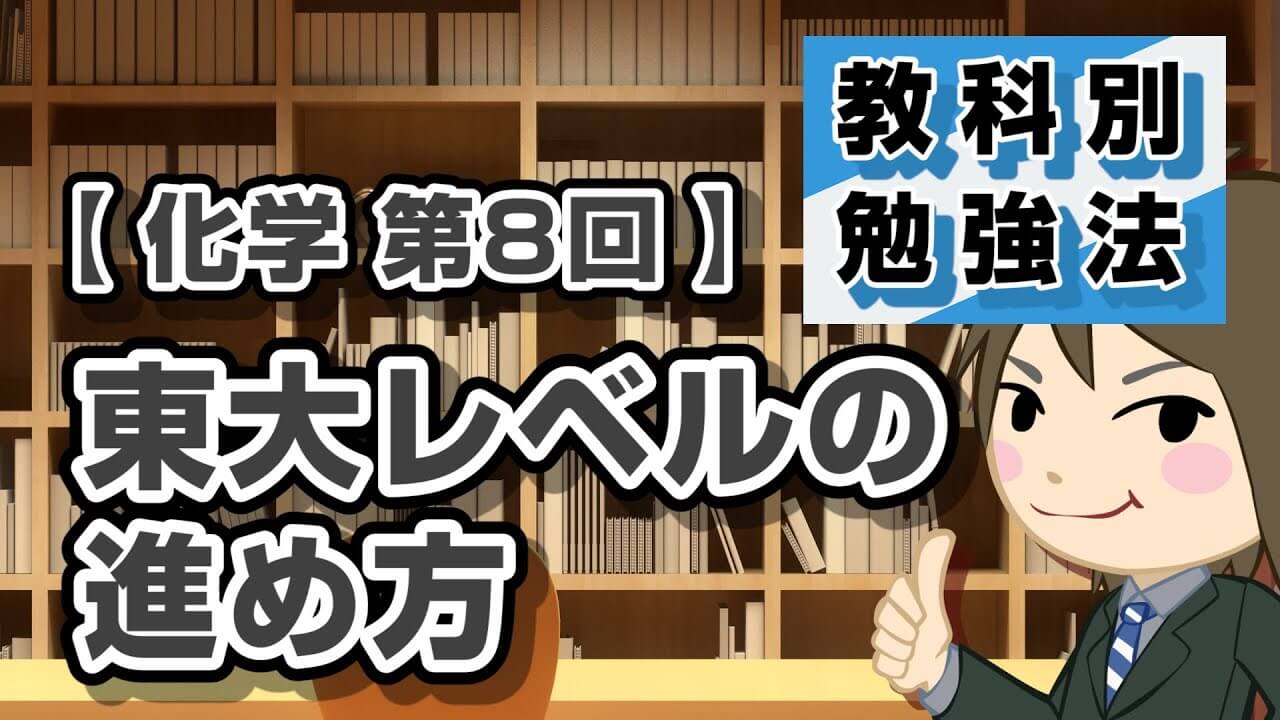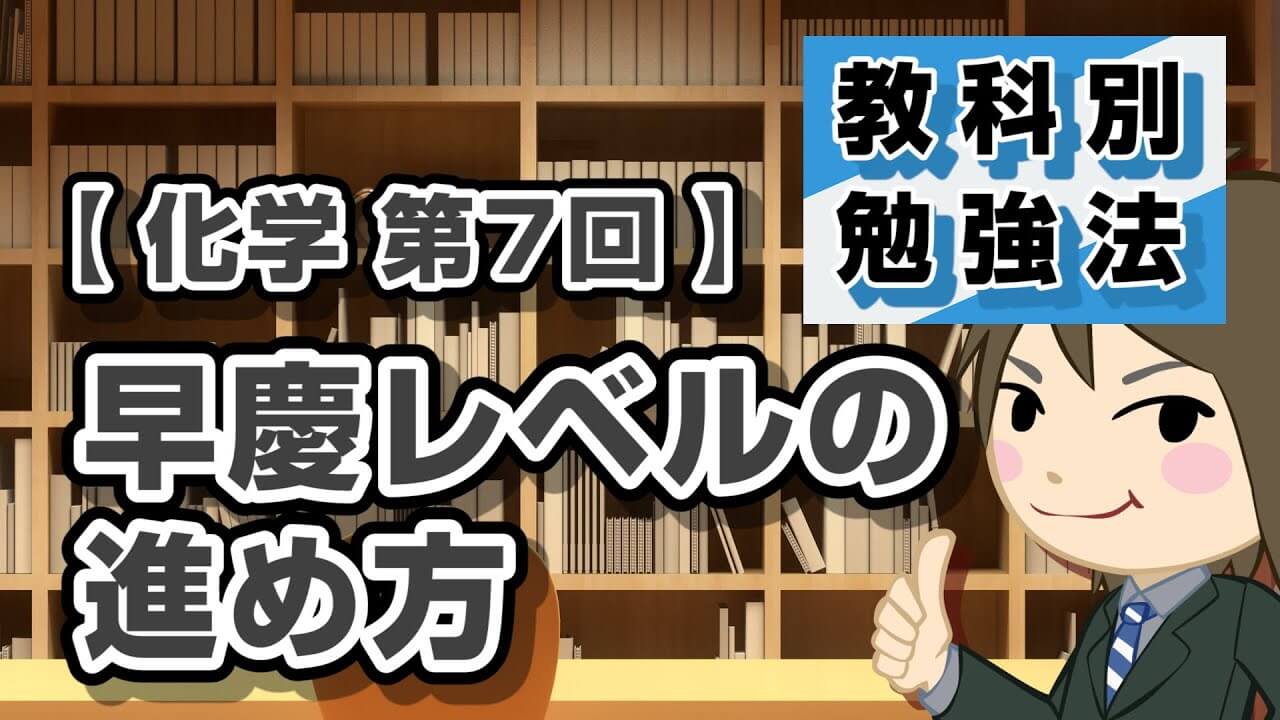化学で「同位体」と「同素体」の知識を問われることがありますが、皆さんは区別をつけられているでしょうか?
化学は覚えるだけでなく、理解し自分で解けるようにならないと得点することができない単元も多いですが、同位体と同素体は覚えるだけで得点することが可能なため化学が苦手な方こそ得意にしていただきたいです。
この記事では、同位体と同素体の違いについて解説した後、同位体と同素体それぞれについて覚えておいてほしい内容をまとめています。
この記事を読んで、同位体と同素体を得意にしよう!
同位体と同素体の違いとは?
それではまず、「同位体」と「同素体」の定義と違いについて解説していきます。
名称としては1文字しか変わりませんが、大きな違いが見られるためしっかりと理解し暗記するようにしましょう!
同位体の定義
同位体は「アイソトープ」とも呼ばれるため、どちらの名称も覚えておく必要があります。
同位体の定義は、例えば以下のようなものがあります。
同位体,同位元素ともいう。原子番号が等しく,質量数が異なる原子または原子核を互いに同位体であるという。
原子番号が同じということは陽子の数も同じであり、一方質量数が異なることから中性子の数も異なることが特徴です。
同素体の定義
一方、同素体の定義は例えば以下のようなものがあります。
同じ元素の単体でありながら,構成する原子の配列,結合の仕方が異なるため,異なった性質を示す単体が2種以上存在するとき,それらを互いに同素体という。たとえば,ダイヤモンドと石墨,酸素とオゾン,黄リンと赤リンなど。
つまり同素体は、同じ元素からなる単体で反応性など化学的性質が異なる物質同士のことであり、化学性質が異なる点が入試で出題されることが多いです。
同位体と同素体は「原子核か単体か」が違う!
以上のことをまとめると、どちらも同じ元素に複数の種類があることがわかります。
違いに着目して整理すると、
・「同位体」は原子核の中の中性子の数により種類がある
・「同素体」は単体の化学的性質に種類がある
といえるでしょう。
同位体は違いを目で確認することができませんが、同素体は形や色などが異なるため目で確認することができる点も違いの1つです。
同位体について詳しく解説!
それでは同位体について詳しく解説していきます。
同位体にはいくつか暗記すべき単語があるため、しっかりと名称と定義を覚えるようにしましょう!
また、存在比・放射性同位体のどちらも計算問題が出題されることがあるため、必ず手持ちの問題集で練習してください。
同位体|存在比
同位体は、全ての同位体が同量存在しているわけではありません。
今回は同位体の代表例として水素(H)を元に解説しますが、水素・重水素・三重水素という名称も時々入試で出題されることがあります。
・水素 1 1 H
中性子の数が0で、存在比は99%
・重水素 2 1 H
中性子の数が1で、存在比は1%
・三重水素 3 1 H
中性子の数が2で、存在比は微量
また、存在比についての計算問題が出題されることがあるため、問題集で練習するようにしましょう!
同位体|放射性同位体
放射性同位体とは、原子核が不安定で放射線を出しながら崩壊(壊変)していくもののことです。
放射性同位体は、ラジオアイソトープという別名もあります。
遺物の年代測定の計算問題が出題されることがあるため、必ず演習問題を解くようにしてください。
同素体について詳しく解説!
同素体のある元素はS(硫黄)・C(炭素)・O(酸素)・P(リン)の4つのみであり、これらの頭文字から「SCOP(スコップ)」と覚える方が多いです。
それぞれについて、
・同素体の種類と名称
・同素体の化学的性質
を覚えるようにしましょう!
また、同素体は見た目が異なることも多いため、資料集などで写真を確認すると暗記しやすくなるためおすすめです。
同素体|S(硫黄)
S(硫黄)の同素体は、斜方硫黄・単斜硫黄・ゴム状硫黄の3種類があります。
それぞれについて、以下の表の内容を覚えるようにしましょう!
| 化学式 | 構造 | 安定 | 色 | その他特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 斜方硫黄 | S8 | 環状分子 | 非常に安定 | 黄色 | 八面体状結晶 |
| 単斜硫黄 | S8 | 環状分子 | 不安定 (放置すると斜方硫黄になる) |
黄色 | 斜状結晶 (結晶が崩れた形) |
| ゴム状硫黄 | SX | 長鎖状分子 | 不安定 (放置すると斜方硫黄になる) |
黄色 | ゴムに似た弾性を持つ |
斜方硫黄が最も安定した形であり、単斜硫黄とゴム状硫黄は放置すると斜方硫黄になる点が特徴です。
見た目による違いがわかりやすいため、必ず資料集やインターネットなどで画像を確認するようにしてください。
同素体|C(炭素)
C(炭素)の同素体は、ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン・カーボンナノチューブの4種類があります。
ダイヤモンドは宝石として使われ、黒鉛は鉛筆の芯として用いられているため、日常生活で見る機会の多い同素体となります。
C(炭素)の同素体については、以下の点のように整理できます。
| 化学式 | 色 | 性質 | |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンド | C | 無色透明 | ・全物質中で最も硬い ・電気を通さない |
| 黒鉛 (グラファイト) |
C | 黒 | ・やわらかくもろい |
| フラーレン | C | 黒 | ナノテクノロジーに利用される |
| カーボンナノチューブ | C | 半導体として用いられる |
同素体|O(酸素)
O(酸素)には、酸素(O2)とオゾン(O3)の2種類があり、こちらも比較的日常的に用いられることが多いです。
| 化学式 | 色 | におい | 形 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 酸素 | O2 | 無色 | 無臭 | 直線型 | 物を燃やす働き(助燃性)あり |
| オゾン | O3 | 淡青色 | 特異臭 | 折れ線型 | (紫外線吸収効果あり) |
特性が大きく異なり、特性がわかる実験が出題されることもあるため、どちらか問われても答えられるようにしておきましょう!
同素体|P(リン)
P(リン)には、黄リンと赤リンの2種類があります。
| 化学式 | 色 | 特性 | |
|---|---|---|---|
| 黄リン | P4 | 黄色 | ・自然発火 ・水中保存 ・有毒 |
| 赤リン | PX | 赤色 | 安定している |
黄リンは空中で放置すると自然発火する可能性があるため、水中に保存します。
また、黄リンは真空中で加熱すると赤リンになります。
一方赤リンは、マッチの横についておりマッチに火をつける際に使用する物質として用いられていることからも分かる通り、毒性はなく自然発火もしません。
同位体と同素体の違い|まとめ
この記事では、
・同素体と同位体の違い
・同位体の存在比と放射性同位体について
・同素体SCOP
を解説しました。
化学では知識を整理し暗記することが重要なため、この記事を何度も読んで知識を整理し暗記した後、問題集を使って知識を定着させましょう!
武田塾では、勉強方法や勉強戦略を入塾の有無に関わらず、無料受験相談にて1人ひとりにあった個別相談を行っています。
全国に校舎があるためお気軽に最寄りの校舎にお問い合わせください。
まだ受験勉強を本格的に始める前の高校1年生も利用可能なため、お気軽にお問い合わせください。