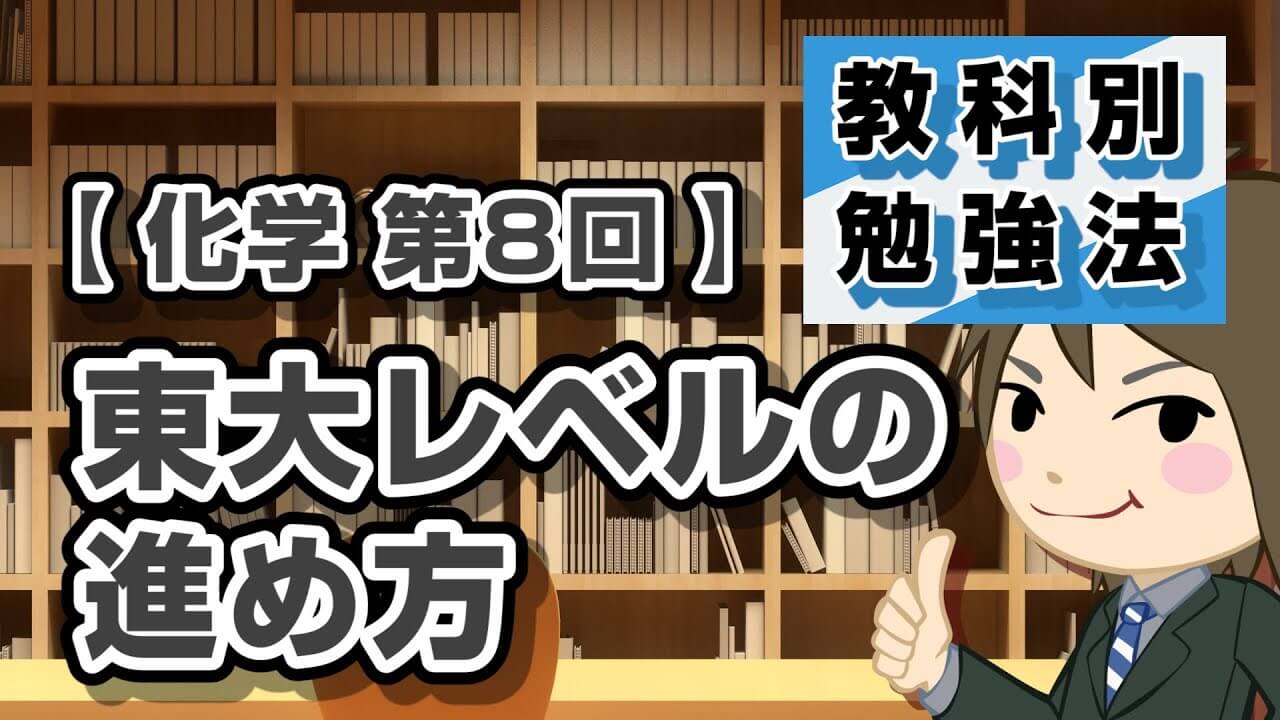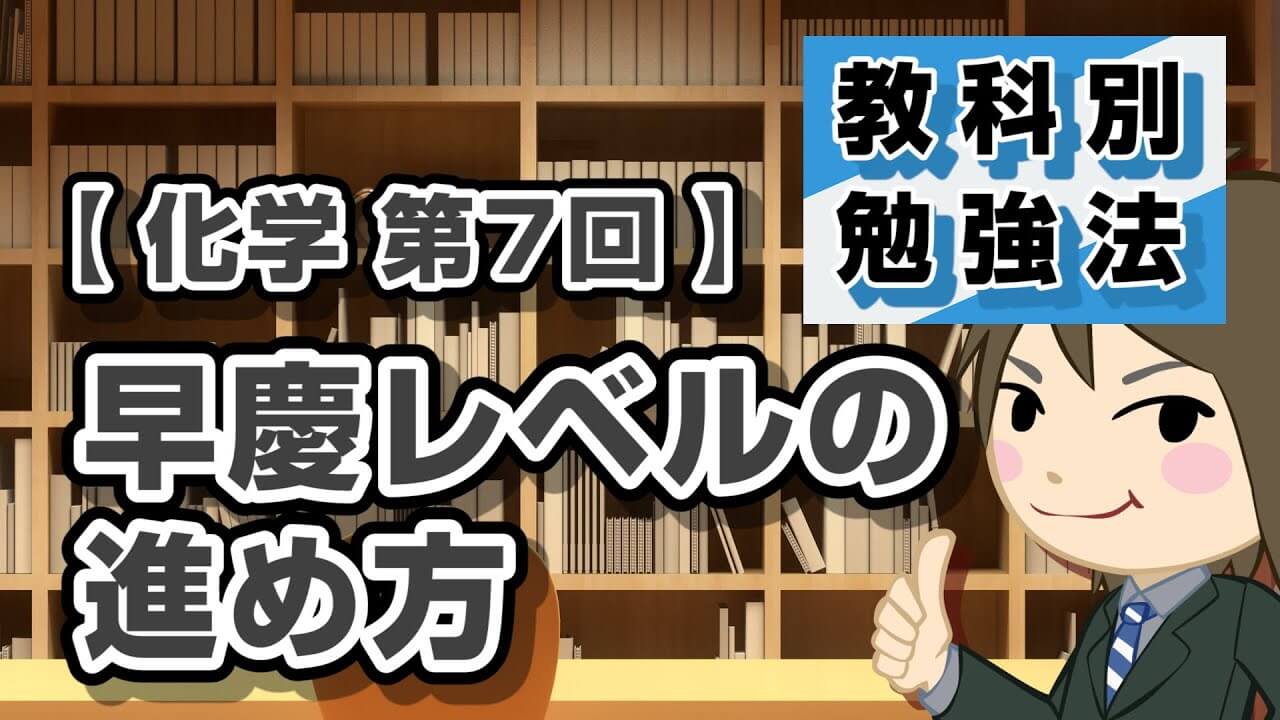化学を勉強している方で、
「化学って苦手!」
「化学結合って何?何個あるの?」
「共有結合とイオン結合ってどう違うの?」
と思っている方もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、化学結合の4つの種類について簡単に解説した後、共有結合とイオン結合についてより詳細に解説をしています。
分子式や組成式の違いなども解説したため、化学の用語が苦手な方や化学結合を詳しく知りたい方におすすめの内容です。
化学の勉強を始めたばかりの方で、どの参考書を使って勉強したら良いか悩んでいる方は以下の記事もあわせてチェックしておくと良いでしょう。
化学結合の種類とは?
化学結合には、
・共有結合
・イオン結合
・金属結合
・分子間力
の4つの種類があります。
これらの強さは一般的に、共有結合>イオン結合>金属結合>分子間力の順になっており、これらの強さの比較も覚えるようにしてください!
ここではそれぞれの化学結合について、簡単に用語の確認をします。
化学結合の種類とは?|①共有結合
共有結合とは、「各原子が電子を出し合って電子対をつくり、その電子対を共有することによってできる結合」です。
共有結合は電子を受け取ろうとする傾向の強い原子間で生じる結合のため、非金属元素と非金属元素で生じます。
共有結合の詳しい内容は「共有結合とは?」をチェック!
化学結合の種類とは?|②イオン結合
イオン結合とは、「一つの原子から別の原子へ電子が移動して生じた陽イオンと陰イオンの静電力による結合」です。
原則金属元素と非金属元素が結合するときに生じる結合ですが、例外としてNH₄⁺(アンモニウムイオン)が含まれる際には非金属元素のみでもイオン結合になります。
イオン結合の詳細は「イオン結合とは?」をチェック!
化学結合の種類とは?|③金属結合
金属結合はその名の通り「金属原子同士の間にできる結合」のことで、金属元素と金属元素の間で生じます。
また、金属結合によってできた物質を金属結晶と呼び、金属結晶はイオン結合同様原子がある限り結合し続けます。
分子のようにひとまとまりにならないため、金属の単体はAl・Ag・Naなどのように組成式で表します。
化学結合の種類とは?|④分子間力
分子間力とは「分子同士の間に働く力」のことであり、水素結合・極力引力・ファンデルワールス力の3種類の総称です。
この分子間力は、原子間の間で生じる共有結合・金属結合・イオン結合に比べて非常に弱い力になっています。
分子間力の中では、水素結合>極性引力>ファンデルワールス力という強さの順番も覚えるようにしましょう!
共有結合とは?
ここでは共有結合について、
・結合の仕組み
・結合の種類
・分子式の作り方
について解説していきます。
共有結合は化学結合の中でも基本中の基本のため、必ず内容を理解し手持ちの参考書を使って練習問題も解くようにしてください!
共有結合とは?|結合の仕組み
先述しましたが共有結合とは、「各原子が電子を出し合って電子対をつくり、その電子対を共有することによってできる結合」のことです。
電子式を描いた際にペアになる電子を持たない電子を「不対電子」と呼びますが、共有結合はお互いの不対電子を2つの原子が共有することにより形成される結合です。
具体例としては、以下のようなものがあります。
NH₃・H₂O・HF・CH₄
共有結合とは?|結合の種類
共有結合には3つの種類があり、それぞれの定義は以下の通りです。
- 単結合
- 二重結合
- 三重結合
原子間が1つの共有電子対で結びついている共有結合のこと
原子間が2つの共有電子対で結びついている共有結合のこと
原子間が3つの共有電子対で結びついている共有結合のこと
これらは電子式を描いた際に、「共有電子対が何個あるか」により結合の種類を判断することが可能です。
具体例としては、単結合がNH₃(アンモニア)、二重結合がCO₂、三重結合がN₂などがあげられます。
共有結合とは?|分子式の作り方
まず分子式とは、分子を構成する原子の種類と数を表したものです。
例えばNH₃(アンモニウム)はN(窒素)とH(水素)という原子を使い、Nを1つとHを3つ使ってひとまとまりになっていることを表しています。
Nは3つの不対電子を持ち、Hは1つの不対電子を持つため、Nのそれぞれの不対電子に1つずつHが対応するためN1つに対しHが3つ必要になります。
各原子の不対電子の数がわからない方は、教科書で確認するようにしてください!
イオン結合とは?
ここではイオン結合について、イオン結合で覚えてほしい用語を紹介しながら結合の仕組みと組成式の作り方について解説します。
化学は用語の定義をしっかり覚えて判断できることが重要なため、分からない用語があった際には教科書や参考書で確認するようにしてください。
イオン結合|結合の仕組み
イオン結合は陽イオンのプラスと陰イオンのマイナスが引き合って静電気力によって結合しています。
この静電気的な引力のことをクーロン力といい、クーロン力によって結びついた結合がイオン結合です。
陽イオンと陰イオンの区別は、以下の通りです。
- 陽イオン
- 陰イオン
単原子イオン:金属元素
多原子イオン:NH₄⁺のみ
単原子イオン:非金属元素
多原子イオン:NH₄⁺以外
受験で覚えなければならない単原子イオン・多原子イオンの名称や価数に関しては教科書や参考書で必ず復習するようにしてください!
イオン結合|組成式の作り方
組成式とは、構成イオンの種類とその数の割合を最も簡単な整数比で表したものです。
組成式の作り方は、以下の通りです。
- 陽イオン・陰イオンの順に並べる。
- 陽イオンと陰イオンのプラスマイナスが一致するように数の比を求める。
- 2.の比を元素記号の右下に書く。(比が1の場合は省略する)
例えばBa(OH)₂(水酸化バリウム)は、Ba²⁺のプラスが2個とOH‐のマイナス1個×2で、プラスマイナスが揃うためBa(OH)₂となります。
【化学結合】イオン結合と共有結合|まとめ
今回は、
・化学結合の4つの種類について簡単に解説
・共有結合の結合の仕組みと種類、分子式の作り方
・イオン結合の仕組みと組成式の作り方
について解説をしました。
化学の勉強では、用語の定義や使い方を丸暗記するのではなく理解しながら覚えて使えるようにすることが重要になります。
武田塾では、志望校のレベル別に「どの参考書をどの順番で勉強していけばいいのか」を無料で公開しているため、化学の勉強方法に悩んでいる方は以下の記事も是非ご覧ください。
また化学の勉強方法はもちろん、受験勉強全般で相談したいことがある方に向けて、武田塾では全国の校舎で無料受験相談を実施しているためお気軽にお問い合わせください。