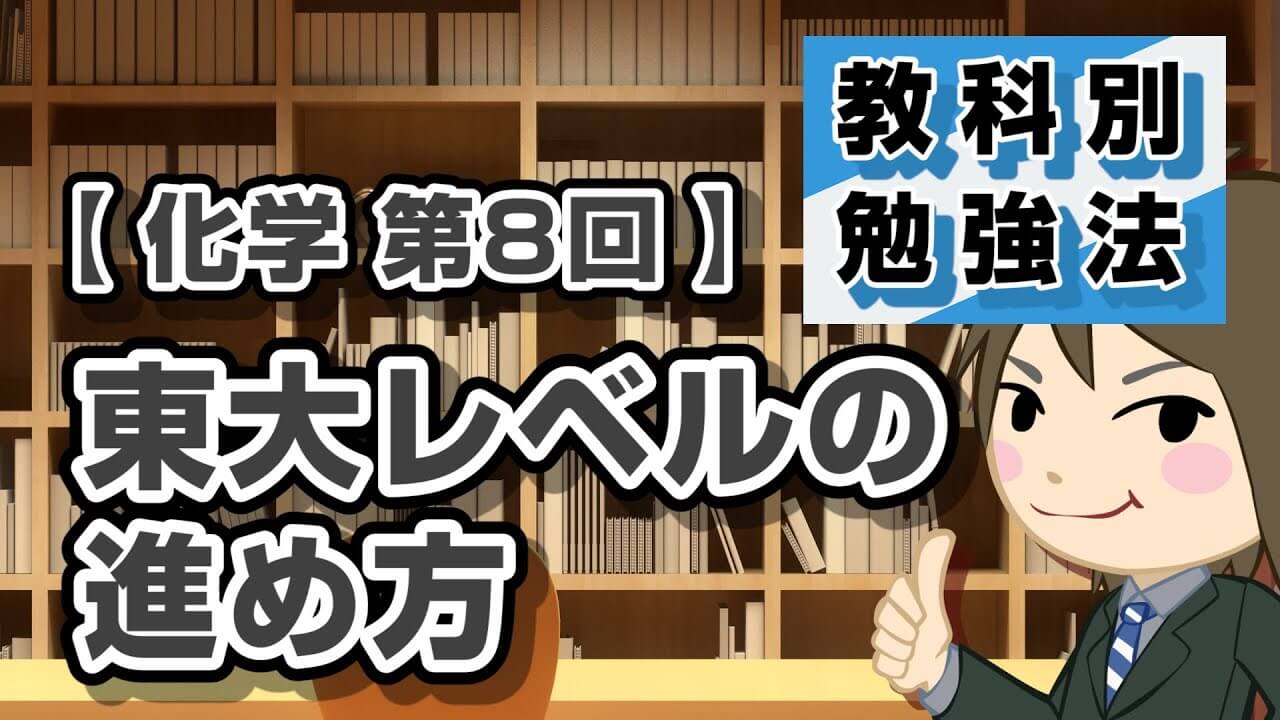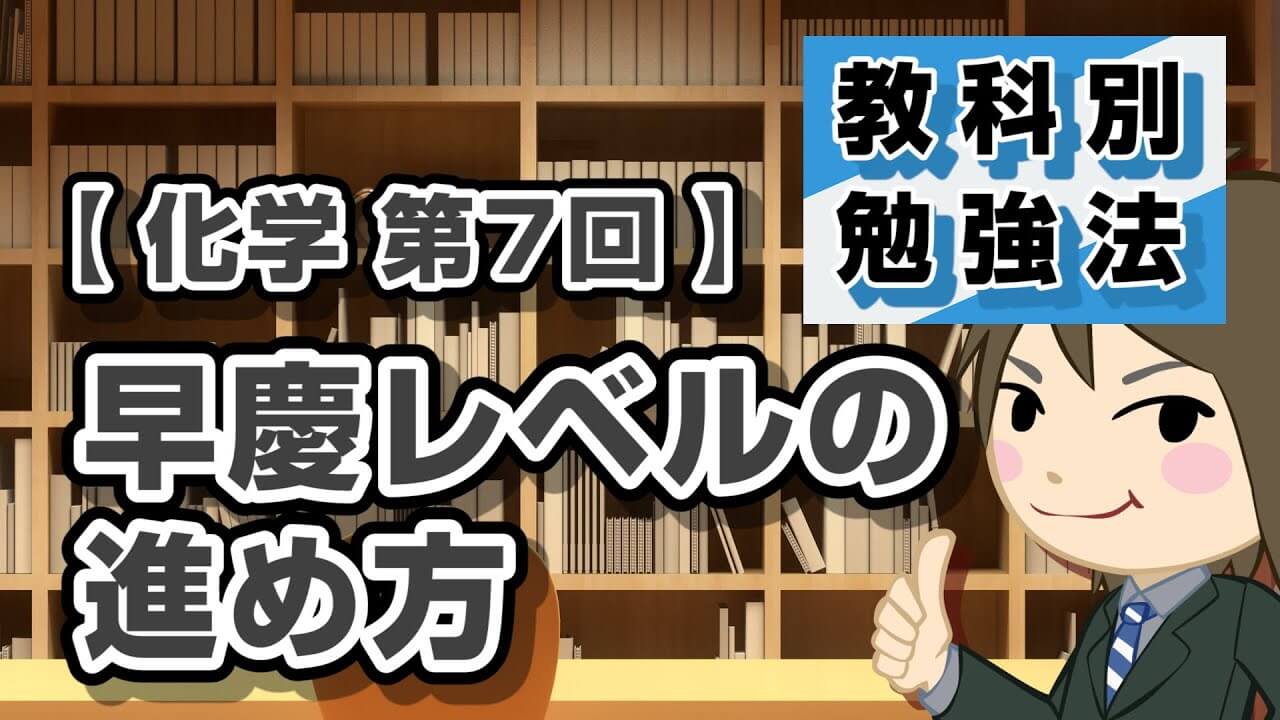化学や化学基礎の勉強では同じ単語が異なる使われ方をしている時があり、その判断を誤ると問題文の理解すらできなくなることがあります。
化学基礎の勉強をしている時に、
「同じ酸素という単語なのに、元素として使われる時と単体として使われる時がある?どういうこと?」
「元素と単体に分類せよという問題がさっぱり解けない」
と思った経験がある方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は元素と単体の違いと、それぞれの定義を解説した後、演習問題を掲載しました。
この記事を読んで、元素と単体の区別を得意にしましょう!
元素と単体の違いとは?|触れるかどうか
元素と単体の違いを一言で言うと、「触れるかどうか」です。
触れる場合や化学反応を起こす場合は単体を指し、そうでない場合は元素を表します。
以下の文章では元素と単体を同じ単語として用いていますが、文の前半が単体として使われ、文の後半は元素として用いています。
・単体のH2(水素)は、H(水素)からできている。
・C(ダイヤモンド)は、C(炭素)からできている。
・単体のO2(酸素)は、O(酸素)からできている。
つまり、以下のように判断することが可能です。
【元素】
物質の成分である原子レベルを表している(元素記号そのもの)。
【単体】
具体的な物質のこと。
問題文で化学反応を起こすことが書いてあれば、基本的にこちらを指します。
まずはイメージを掴み、その後正確な定義を覚えるようにしましょう!
元素と単体についてそれぞれの定義を確認しよう!
元素と単体の違いについて簡単に判断する方法を紹介しましたが、ここでは定義を含めた詳しい違いについて解説していきます。
元素の定義や単体の定義の文章は正誤問題で出題されることもあるため、定義もしっかり覚えるようにしましょう!
元素の定義|物質の基本的な成分
元素とは物質の基本的な成分のことであり、元素は元素記号を用いて表すことになっています。
化学や化学基礎を勉強している方は周期表を暗記した経験があると思いますが、この元素と元素記号を1つの表にしたものが周期表です。
周期表は化学・化学基礎を勉強する上で最も大事な項目と言っても過言ではありません。
「元素記号・名称・族ごとの性質・金属/非金属の見極め」など、周期表で覚えなければならないことは必ず全てしっかりと覚えるようにしましょう!
単体の定義|1種類の元素から構成された物質
単体の定義は、1種類の元素から構成された物質です。
単体は純物質の一部で、さらに単体と化合物に分かれていますが、この違いも出題されることがあるため以下の表を覚えるようにしましょう!
| 1種類の元素から構成された物質 | 単体・純物質 |
|---|---|
| 2種類以上の元素から構成された物質 | 化合物 |
単体と化合物の違いを考える時は、元素が1つかそれ以上かで判断することが可能です。
例えば以下のようなものがあります。
単体:H2、O2など
化合物:H2O、NaCl、CO2など
化学式を書いて考えることで、単体と化合物は簡単に判断することが可能です。
元素と単体にまつわる演習問題
元素と単体の定義や違いの判断方法がわかったところで、実際に演習問題を解いてみましょう!
化学・化学基礎の勉強では、
①内容を理解する
②問題を解いて理解度を確認する
③間違えた問題から、覚えていなかった知識や解き方を覚える
の3つのステップが重要なため、必ず演習問題を解き完璧に理解するようにしてください。
演習問題①|基礎
以下の文章の下線部分が、元素として使われているか、単体として使われているか判断せよ。
「カルシウムは、人体の骨や歯に多く含まれている。」
触れることができるのは骨や歯であって、その中に含まれているカルシウムは触ることができません。
よって、カルシウムは元素として用いられています。
「含まれている」という単語を用いて記載されている場合は、はじめに元素を疑って判断してみましょう!
演習問題②|基礎
以下の文章の下線部分が、元素として使われているか、単体として使われているか判断せよ。
「二酸化炭素は、炭素と酸素から構成されている。」
二酸化炭素はCO2として表されますが、C(炭素)とO(酸素)という元素記号を用いて表されています。
これらのCとOは触ることができないため、上記の文章では元素として用いられていることがわかります。
演習問題③|基礎
以下の文章の下線部分が、元素として使われているか、単体として使われているか判断せよ。
「生物は呼吸によって、酸素を取り入れている。」
生物が取り入れている酸素は空気中にあり、触ることができるため、この場合の酸素は単体として使われています。
また、上記の酸素は化学式を用いてO2として表されます。
演習問題④|応用(化学反応)
次は少し難しい応用問題です。
以下の文章の下線部分が、元素として使われているか、単体として使われているか判断せよ。
「窒素と水素を反応させると、アンモニアができた。」
上記の文章は、N2とH2を反応させると、NH3ができた。」と言い換えることが可能です。
つまり、物質の窒素と水素を反応させて物質のアンモニアができていることから、上記は単体の意味で用いられています。
このように化学反応の問題の際には、単体として用いられていることが多いです。
化学反応の問題は苦手に思う方も多いですが、「触れるかどうか」を考えたり、「化学反応式」を考えたりすることで簡単に判断することが可能です。
化学反応式はその他の単元でも用いられるため、この記事を読んでいて「化学反応式の書き方や読み方がわからない」と思った方はすぐに復習するようにしてください!
【化学基礎】元素と単体の違い|まとめ
今回の記事では、化学基礎から元素と単体の違いについて解説しました。
化学基礎のなかでも基本的な内容ですので、以下の3つについてしっかりと覚えておきましょう。
【元素と単体の違い】
触れるかどうかで判断しよう!
【元素の定義】
物質の基本的な成分
【単体の定義】
1種類の元素から構成された物質
化学や化学基礎の勉強では問題が解けることだけでなく、用語の定義を覚え正確に判断したり使用できるようにしたりすることも重要です。
勉強している際に「わかりづらいな」「似ているな」と思うような単語は、基本的に他の多くの受験生も苦手とするため入試で出題される頻度も上がると考えましょう。
一つひとつの用語について、順番に確実に覚えていくようにしましょう!
参考書の選び方・受験勉強の戦略など一人ひとりにあった勉強方法について、武田塾のスタッフに相談することができる「無料受験相談」を全国の武田塾の校舎で実施しています。
お気軽に無料受験相談から最寄りの校舎にお問い合わせください。