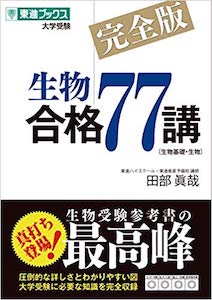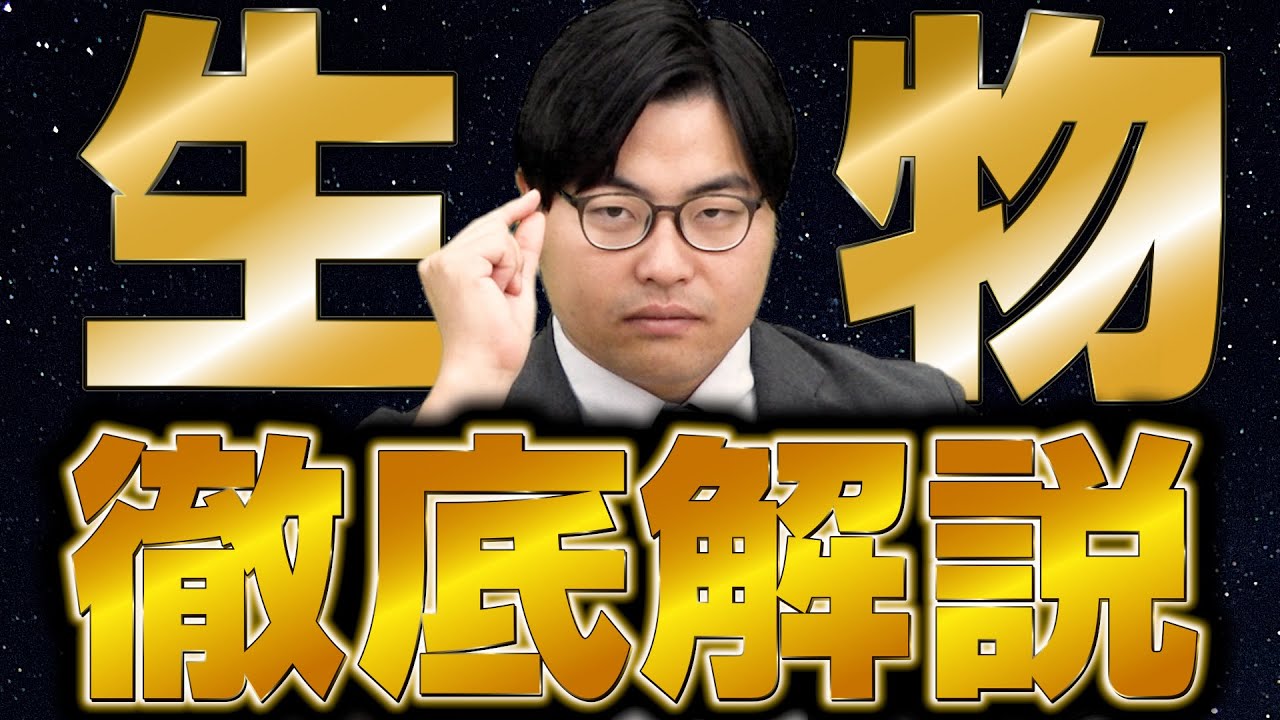今回は生物に関する勉強方法を紹介します。
生物は暗記で乗りきれる!と唱える人もいることから、文系受験生にも選択されることが多い教科です。
しかし、いざ選択したは良いものの、得点が伸び悩んでいるという方もいらっしゃることでしょう。
そこで今回は、生物の勉強法やおすすめの参考書について解説していきます。
生物の勉強法
生物は暗記が重要となる強化ですが、ただやみくもに登場する語句を覚えれば合格点が取れるわけではありません。
そこで以下では、生物の勉強法を4つ解説していきます。
以下の方法を取り入れ、生物を得意科目にしていきましょう。
1.暗記の際は周辺情報にも目を向けよう!
生物を覚える際に、ただ用語を覚えているだけでは実際の入試には使いづらいです。
その用語自体の説明や図などにも目を配り、一つの用語に様々な知識をつけるようにしていきましょう。
生物は社会の科目ではないです。 文系受験生は社会の科目と同じ気分で勉強すると危険です。
2.暗記だけの科目と思うな!
生物で難問といわれる問題は、実験考察問題の場合がほとんどです。
実験考察の問題を解く場合には、知識以上に考え方やその場での情報収集能力が問われるため、 難しい問題集の暗記にはならないように注意してください。
生物に関しては難しい問題集の暗記をしても意味が無いので、なるべくたくさんの新しい問題にチャレンジしていきましょう。
3.問題演習を積んだら穴を埋めていこう
生物の問題がある程度答えられるようになってきたら、残りの知識を補完していきましょう。
生物は理系科目といっても、知識がかなり重要になってくるので暗記を徹底してください。
4.覚えにくいものは英単語のように覚えよう!
英単語の覚え方の記事でも解説しましたが、暗記を行う際にはまず自分に合った暗記方法を確立することが先決です。
声に出す・読む・書く・ゴロで覚える・連想で覚えるなど様々な暗記方法があります。
万人に受ける暗記法はないので、自分にあったものを見つけ出して見てください。
生物のおすすめ講義系参考書
ここからは、生物のおすすめ講義系参考書を紹介します。
生物の参考書を講義系、用語集、問題集といったように分けてご紹介しているので参考にしてみてください。
生物の成績を上げて、志望校合格を目指しましょう。
忘れてしまった高校の生物を復習する本

【特徴】
「忘れてしまった高校の生物を復習する本」は高校生物の内容を非常によくまとめた参考書です。
生物という教科をとっつきにくいと考えている人に読んで欲しい1冊です。
これ1冊だけでは不十分なので、あくまでも生物の概要を思い出して勉強するきっかけとして使用することをおすすめします。
本格的な勉強に入る前にこの参考書を使うと、頭の中を整理させることができます。
【使用法】
本格的に受験勉強を始める前、もしくは受験勉強の気分転換に読むことをおすすめします。
内容が非常によくまとまっているので復習のための1冊としても使うことができます。
基礎的なことであっても覚えにくい箇所などを簡潔に分かりやすく説明しているので、頭の中の情報を整理しながら読むと良いです。
1冊読み終わったらより細かい解説が載っている講義系の参考書に進みましょう。
生物合格77講
【特徴】
「生物合格77講」はこの1冊のみで生物を網羅出来るほど詳しい解説が載っている講義系参考書です。
最新の全教科書に対応しているガイド本なので、教科書の中で何を覚えればいいのかが分かるような仕様となっています。
解説は論理的な説明がなされているのでただ知識を暗記するだけでは終わりません。
生物を完璧にしたい人、細かい知識まで覚えたい人におすすめな1冊となっています。
【使用法】
繰返し通読することで知識のインプットをしていきましょう。
ただ暗記するのではなく、どうしてそうなるのかなどの思考プロセスまで覚えられると良いでしょう。
また、解説が詳しすぎるので1度で覚えようとせず、何回も読むことが攻略の鍵です。
また、分からないことがあったら調べるといったように辞書的に使うこともおすすめです。
山川喜輝の生物が面白いほどわかる本

【特徴】
「山川喜輝の生物が面白いほどわかる本」は、断片的な情報をひとつながりのストーリー状にして解説している講義系の参考書です。
ストーリー状になっているのでインプットしやすく忘れにくい仕様となっています。
授業の予習復習に加えて、共通テスト対策、二次・私大対策まで広く使える1冊です。
【使用法】
何度も繰返し読むことで知識を定着させていきましょう。
重要な部分が赤字で書かれているので、赤シートを使って隠して確認することで、知識のアウトプットの練習もすることができます。
また、直接書き込むことができる「書き込みシート」が付いているので、こちらでも知識の出し入れをして定着させていきましょう。
一度で覚えようとせず、何度も繰返して暗記していくことがおすすめです。
生物のおすすめ用語集
生物の知識を講義系参考書で学びながら、知識を整理していく必要があります。
そんな時におすすめなのが用語集です。
ここからは知識のインプットにおすすめな用語集を1冊紹介します。
生物 必修整理ノート
【特徴】
「生物 必修整理ノート」は生物の用語を穴埋め形式で勉強していくことで用語のインプットができる参考書となっています。
この参考書を使って用語を覚えていくことで、問題演習に向けた知識を蓄えることができます。
ただ、この参考書だけで理解しようとすると不足している部分もあるので、講義系の参考書や問題集と併用することをおすすめします。
【使用法】
書き込み式の部分は別のノートに回答を書き、知識が定着しているかをチェックしましょう。
その後、講義系の参考書などを用いて、間違っている部分を確認します。
一通り終わったら、書き込みの部分に赤色のペンで答えを書いていきましょう。
そして、赤シートで赤字の部分を確認していくと、何度もインプットとアウトプットの練習をすることができます。
生物のおすすめ問題集
ここからは、生物のおすすめな問題集をご紹介します。
問題集に着手する時は、ある程度知識を付けた状態が望ましいです。
もしまだ知識を覚えきれていないという方は先を急がずに1つ前の参考書に戻りましょう。
生物問題集合格177問【入試必修篇】

【特徴】
「生物問題集合格177問【入試必修篇】」は詳細な解説が付いている問題集です。
生物の知識が一通り身についた人が取り組むと知識のアウトプットとなり、さらに知識が身につくでしょう。
詳細な解説が付いているので、どうしてその回答になるのかについてのプロセスを理解するのに使ってみてください。
【使用法】
まずは一通り解いてみましょう。
その後、解答を見ながら丸付けをして、解説を隅々まで読んでいきましょう。
解説には解法の着眼点、道筋、注意点などが書いてあるので、どうしてその解答になるのかについての解答プロセスも確認できると良いでしょう。
そして、完璧になるまで繰返し解くようにしましょう。
大森徹の最強講義117講 生物
【特徴】
「大森徹の最強講義117講 生物」は、東京大学や私立医学部レベルの難関大対策ができる問題集です。
大きな特徴として、知識問題に加えて計算問題や実験考察、論述問題等も扱われています。
この問題集に取り組むにはある程度の力が必要になってくるので、MARCHや地方国公立レベルの力をつけてから取り組むようにしましょう。
【使用法】
難関大学対策に使われることの多い参考書となっているので、大学入試標準レベルの力をつけてから取り組むようにしましょう。
各講が60分の講義と同じぐらいの分量とされているので、各講議にじっくりと時間をかけて丁寧に取り組んでいくと良いです。
各講で最も理解するべきポイントが「最強ポイント」としてまとめられているので、それをしっかり押さえながらやっていきましょう。
2周目以降はその「最強ポイント」を重点的に復習すると効率的に学習できます。
大森徹の最強講義159問 生物
【特徴】
「大森徹の最強問題集159問」は早慶・東大レベルの実力が求められる非常にレベルの高い問題集となっています。
そのため、入試標準の問題が解けるようになってから取り組むことをおすすめします。
この問題集の中には単元を飛び越えた問題も取り扱われているので、複合した知識を求められる問題にも対応可能になっています。
【使用法】
この参考書は早慶・東大レベルの実力が求められるので、入試標準レベルの問題は解けるくらいの実力を付けてから取り組むことが望ましいです。
一度一通りやってみて、解答解説をじっくり読みましょう。
その時、特に記述の問題ではどのようにすればその回答ができたのかまで考えながら進めると良いです。
論述問題においては、採点基準まで丁寧に書かれているので、そこも確認するようにしましょう。
生物の勉強法と参考書|まとめ
今回、生物の勉強法と参考書についてご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。
生物の知識を暗記する時は、その単語だけでなく周辺の情報も合わせて覚えるようにしましょう。
また、暗記だけでは太刀打ちできない問題も存在するので、問題演習を重ねて対策できるようにしましょう。
参考書は講義系、用語集、問題集と分けてご紹介したので、自分に何が足りないかを判断しながら選ぶと良いです。
【生物】参考書ルートはこちら
参考書ルートは武田塾が考案の自学自習のルート!
志望校合格に必要な参考書と学習の順番が一目でわかるため、自学自習におすすめです。
物をマスターして志望校合格に一歩近づきましょう。